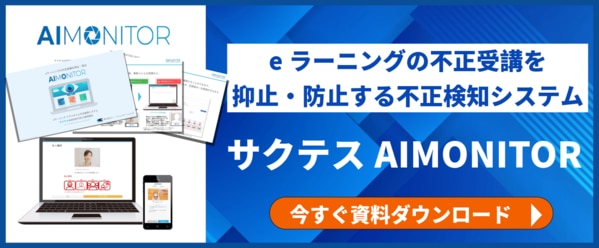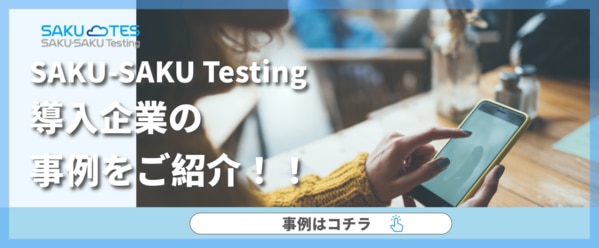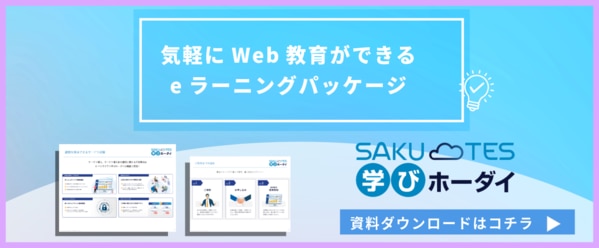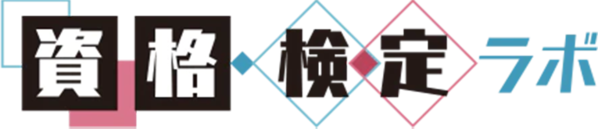ファシリテーターの役割とは?研修や会議を活性化するスキルと上達するコツを解説
「会議や研修で、なかなか意見が出ない」
「参加者が受け身になり、一方通行の進行になっている」
そんなお悩みはありませんか?
そんなときは「ファシリテーター」の存在に注目してみましょう。
ファシリテーターの役割やスキルを改めて知ることで、参加者の発言を引き出し、活発で実りある場づくりが可能になります。
本記事では、ファシリテーターの基本からその効果、上達のコツまでを分かりやすく解説します。
目次[非表示]
- 1.ファシリテーターとは?
- 2.ファシリテーターと司会の違い
- 3.ファシリテーターに必要なスキルとは?
- 3.1.① 聴く力
- 3.2.② 論点を把握し、整理する力
- 3.3.③ 軌道修正する力
- 4.研修におけるファシリテーターの効果
- 4.1.① 参加者の発言が増える
- 4.2.② ゴールが明確になる
- 4.3.③ 参加者から新しいアイデアが生まれる
- 5.ファシリテーションが上達する3つのコツ
- 5.1.① 会議の事前準備を十分に行う
- 5.2.② 会議の目的と時間配分を把握する
- 5.3.③ フラットな立場で会議に参加する
- 6.まとめ
- 7.社員教育にSAKU-SAKU Testingがおすすめ
ファシリテーターとは?

ファシリテーターとは、会議や研修で参加者の意見を引き出し、議論を整理・活性化しながらゴールへ導く進行役のことです。
単なる司会ではなく、意見の対立や沈黙も調整し、参加者が納得感をもって話し合いに関われる場をつくる役割をもちます。
中小企業では、上司主導の一方的な場になりがちですが、ファシリテーターを置くことで多様な意見を引き出し、組織の知恵を形にしていくことができます。
ファシリテーターと司会の違い

司会は、決められた進行スケジュールに沿って会をスムーズに進める役割があります。一方ファシリテーターは、場の空気や参加者の表情を読みながら、意見を引き出し、話し合いが目的からブレないように導く支援者と言い換えることができます。
司会が「予定通りに進める人」だとすれば、ファシリテーターは「対話を深め、建設的な話し合いができるように導く人」といえるでしょう。
参加者の意欲や発言を引き出す点において、両者の役割には大きな違いがあります。
ファシリテーターに必要なスキルとは?

ファシリテーターとして場をうまく進行するには、大きく分けて3つのスキルが必要です。それぞれ解説していきます。
① 聴く力
ファシリテーターには、参加者の発言をしっかり受け止める「聴く力」が欠かせません。ただ話を聞くだけでなく、うなずきや相づち、アイコンタクトなどで「あなたの話を理解しようとしている」という姿勢を示すことで、場の安心感が生まれ、発言が活性化します。
② 論点を把握し、整理する力
多様な意見が出たとき、対立を避けつつ議論を収束させるには、論点を的確に捉え、整理する力が必要です。発言の共通点を見つけ、選択肢を整理しながら、参加者が納得できる方向へと議論を導くのがファシリテーターの重要な役割です。
③ 軌道修正する力
議論が目的から外れたとき、自然に軌道を戻せる力もファシリテーターには必要です。参加者の意見を否定せずに受け止めつつ、心理的安全性を保ったまま話題を整理・誘導できることで、会議全体の質と集中力が高まります。
研修におけるファシリテーターの効果

ファシリテーターがいると、研修の空気や進み方がより良いものになります。ここではファシリテーターがいることの3つの良い変化を紹介します。
① 参加者の発言が増える
ファシリテーターがいると、「みんなが話を聞く」「どんな意見でも言っていい」という安心した空気が生まれます。すると、普段発言が少ない人も、自分の考えを話しやすくなり、自然と意見がたくさん出てくるようになります。
② ゴールが明確になる
ファシリテーターがいることで「この話し合いは何のためにしているのか?」が明確になります。みんなの意見がバラバラになっても、ゴールに向かって話をまとめてくれるので意味のある時間になります。
③ 参加者から新しいアイデアが生まれる
ファシリテーターが場をあたたかくすると、みんなが安心して話せるようになり「そんな考え方もあったんだ!」と、今まで気づかなかった新しいアイデアが見つけやすくなります。
ファシリテーションが上達する3つのコツ
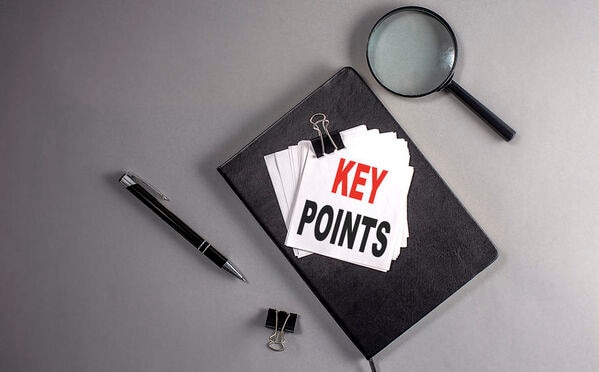
ファシリテーションは、ちょっとしたコツを意識するだけで効果が変わります。ここでは、会議や研修をスムーズに進めるファシリテーションの3つのコツを紹介します。
① 会議の事前準備を十分に行う
ファシリテーションの成否は、会議前の準備にかかっています。まず「この会議は何のために開くのか(スタート)」と「どんな状態になれば終わりか(ゴール)」を明確にしましょう。
課題の背景や必要なアクションを整理しておけば、合意形成までの流れが見えやすくなり、当日の進行もスムーズになります。
② 会議の目的と時間配分を把握する
会議を効果的に進めるためには、事前にアジェンダを作成し、目的や時間配分を明確にすることが大切です。
議題ごとに使える時間や進行の流れを整理しておけば、話が脱線しにくくなり、結論がぶれません。全員が「何のために集まるのか」を理解して参加することで、会議後の行動にもつながります。
③ フラットな立場で会議に参加する
ファシリテーターは特定の意見に偏らず、中立的な立場での進行が求められます。どの意見にも同じように耳を傾け、良い点に注目したり、疑問を投げかけたりしながら、全体でより良い結論を導いていく姿勢が大切です。
発言しやすい空気をつくるために、相槌や要約など、丁寧な聞き方も意識しましょう。
まとめ
会議や研修の場を、もっと実りあるものにしたい。
そう考える中小企業のご担当者にとって、ファシリテーターの視点とスキルは大きな助けになります。
特別な資格がなくても、ちょっとした工夫と意識で始められるのがファシリテーションの魅力です。
まずは小さな会議や研修から取り入れて、社員の意見が自然と集まり、活発な学びが生まれる場づくりをめざしてみてはいかがでしょうか。
社員教育にSAKU-SAKU Testingがおすすめ
社員教育にイー・コミュニケーションズのeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」がおすすめです。
「SAKU-SAKU Testing」は自社で作成した教材を搭載して利用できるので、教育プラットフォームとして活用することが可能です。
また、自社コンテンツを搭載するeラーニングプラットフォームとしての利用以外に、あらかじめ社員教育に必要な教材がパッケージ化されている「サクテス学びホーダイ」など、さまざまなニーズに対応したeラーニングのご提案が可能です。
ご興味がおありの場合はお気軽にお問い合わせください。