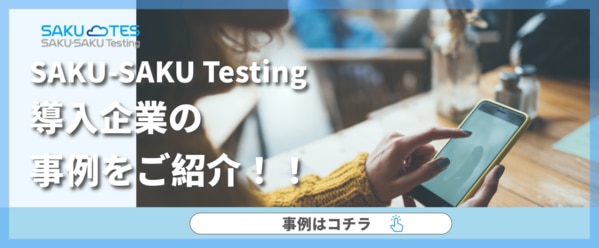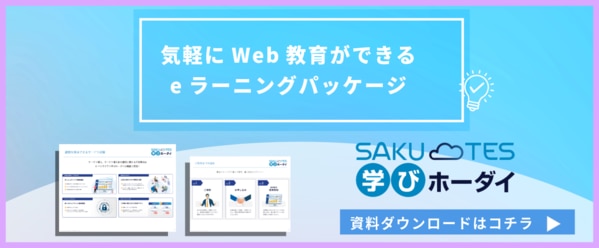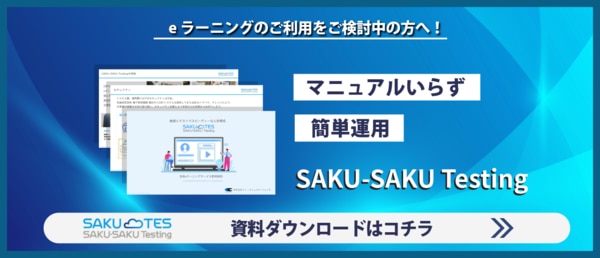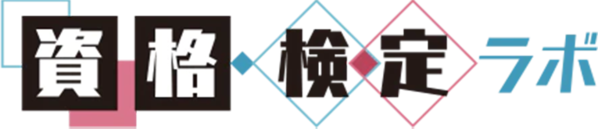人事DXとは?メリットやポイントについて解説
人事DX(HRDX)は、企業の競争力を高めるために欠かせない施策です。DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用することで、業務プロセスの効率化やデータ分析による戦略的な意思決定が可能になります。また、企業文化や社員のエンゲージメント向上を促し、現代のビジネス環境に適応した持続的な成長を実現します。
本記事では、メリットやポイントなどをご紹介しますのでお役立ていただけましたら幸いです。
目次[非表示]
- 1.人事DXとは何か
- 1.1.人事DXにおける基本概念
- 1.2.人事のDX化の重要性
- 2.人事DXで実現できること
- 2.1.データの一元管理ができる
- 2.2.コストや業務プロセスの削減ができる
- 2.3.社員エンゲージメント向上する
- 3.人事DXのメリット
- 3.1.メリット①業務効率化による負担軽減
- 3.2.メリット②データ統合とその活用
- 3.3.メリット③戦略人事の実現
- 4.人事DXの課題
- 4.1.課題①DXの人材が足りない
- 4.2.課題②現在使用しているシステムを変更することが困難
- 4.3.課題③データ収集の難しさ
- 5.成功する人事DXの進め方
- 5.1.目的と課題の明確化
- 5.2.適したツールやシステムの選定
- 5.3.段階的な導入と評価プロセス
- 6.人事DXのポイント
- 6.1.ポイント①全社的なDX推進の一環として進める
- 6.2.ポイント②成果を重視した導入設計
- 6.3.ポイント③社員との協力体制の構築
- 7.人事DXが成功した企業の事例
- 8.効果的・効率的に人事DXを行いたい担当者様は「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
人事DXとは何か

ここでは、人事DXの基本概念や重要性について解説します。
人事DXにおける基本概念
人事DXは、人事領域におけるデジタル化を指し、HRDXとも呼ばれています。従来のアナログ業務をデジタル技術へと移行し、業務の効率化や自動化を実現していきます。これにより、社員情報の管理や評価、スキルの把握などがスムーズになります。特に、HRIS(human resource information system:人材情報システム)の導入が進んでおり、各種データを一元管理し、戦略的な人材マネジメントを支援します。業務プロセスのデジタル化とデータ活用によって、社員のパフォーマンスを最大化することが可能です。
人事DXにより、企業は人的資源を戦略的に管理できるようになります。具体的には、HRIS(人事情報システム)やタレントマネジメントシステムを活用し、社員の情報を効率的に集約して分析します。
人事のDX化の重要性
人事のDX化は、企業においてますます不可欠な要素となっています。働き方が多様化し、柔軟性や迅速な対応が求められる今のビジネス環境において、人事部門の役割は従来以上に重要です。DX化によって、業務の効率化を図ることができ、人事DX化により社員の生産性向上に繋がるのです。
人事DXで実現できること

ここでは、人事DXによって実現できることを解説します。
データの一元管理ができる
データを一元管理することで、適切な人材配置や育成の施策が講じやすくなります。データをもとに人事施策を実施することで、より効果的な採用や育成が可能になります。例えば、過去のデータを基にした採用基準の見直しや、スキルマッピングによる人材育成計画の策定が挙げられます。
また、迅速な意思決定が求められる中で、データに基づいた戦略的な人事施策が可能になるため、経営層との連携も強化されるでしょう。
コストや業務プロセスの削減ができる
コスト削減や業務プロセスの自動化といった面でも、人事DX化は大きなメリットがあります。繰り返し発生する業務を自動化することで、人事部門の負担を軽減できます。手作業を減らし、効率的な運用ができるようになることで、人事部門が本来の業務である戦略的な施策に専念できる環境が整います。
社員エンゲージメント向上する
社員エンゲージメントを向上させるための施策もデジタル技術を通じて実現可能です。エンゲージメント調査やフィードバックの取得が迅速に行えるようになり、社員の満足度を高める施策が策定しやすくなります。
人事DXのメリット

ここでは、人事DXのメリットについてみていきましょう。
メリット①業務効率化による負担軽減
業務効率化は、人事DXの中でも特に顕著なメリットの一つです。不必要な手作業を減らすことで、ペーパーレス化も進みます。特に、給与計算や勤務管理といった労働集約的な業務を自動化することによって、人事部門のリソースが最適化されます。
メリット②データ統合とその活用
データ統合は、人事DXによって実現される重要な特徴の一つです。さまざまな部署やプロセスから集められたデータが一元化され、迅速にアクセスできるようになります。これにより、経営陣は信頼性の高い情報を基にした意思決定が可能になります。
また、集約されたデータを用いて人材分析を行うことで、組織全体のパフォーマンスを把握できます。適切な人材配置や育成プランの策定が進み、持続可能な成長をサポートします。
メリット③戦略人事の実現
人事DXは、戦略人事を実現するための基盤にもなります。デジタルツールにより、社員のスキルやパフォーマンスを迅速に把握できるため、適材適所の人材配置が容易になります。これにより、各社員の能力を最大限に引き出し、組織全体の生産性を向上させることにつながります。
さらに、戦略的な施策やプログラムを円滑に実施するための情報基盤が整うことで、企業の長期的なビジョンに沿った人事戦略が策定しやすくなります。こうした環境を整えることによって、企業は変化に柔軟に対応できる能力を高め、競争力をもつ人材を育成していくことが可能になるのです。
人事DXの課題
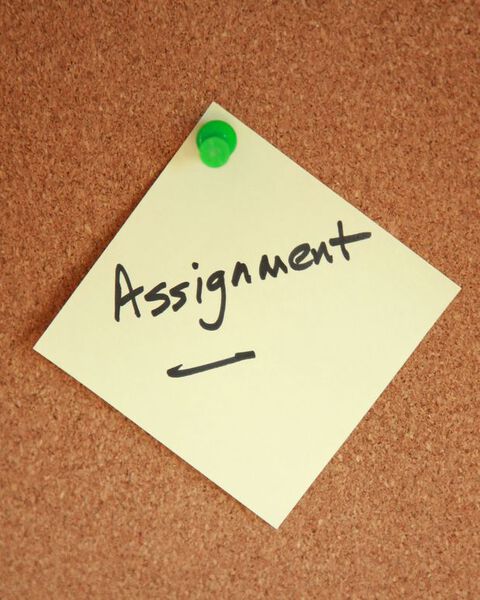
人事DXを進める際には課題もあります。ここでは課題についてみていきます。
課題①DXの人材が足りない
人事DXを推進するうえで、デジタル技術に精通した人材の確保は極めて重要です。しかし、現在の市場ではDXに特化したスキルをもつ即戦力の人材が不足しており、この課題は特に中小企業において深刻です。若手社員を含め実務経験が不足しているケースも多く、結果として企業は新人研修や教育プログラムに多くのリソースを費やす必要があります。
これにより、社員全体のデジタルスキルを向上させる努力が求められますが、その一方で短期間で実績を上げるのが困難な場合が多いのが現状です。そのため、企業は社内の人材を育成する施策のみならず、必要であれば外部からDX人材を採用するという選択肢を視野に入れるべきです。
具体的には、社内教育プログラムを充実させるとともに、外部の専門機関やコンサルタントの力を借りることで、効率的に人事DXを加速させることが期待できます。
最終的に、デジタルスキルの向上は企業競争力を高めると同時に、人事DXの成功を支える基盤となります。そのためには、人材育成と採用の両面で積極的な対策を講じる必要があります。
課題②現在使用しているシステムを変更することが困難
既存の人事システムから新しいシステムへの移行は、企業にとって依然として大きな課題となっています。長期間運用されてきたシステムは、膨大なデータや業務プロセスと深く結び付いているため、その変更には多大な労力を伴います。人事DX化を進めるためには、システム切り替え時に発生する経済的なコストや時間的な制約を十分に考慮し、効率的な計画を策定することが求められます。
特に、新しいシステムへの移行には、既存システムとの互換性や運用上の問題が発生するリスクも含まれています。また、社員には新しい仕組みやデジタルツールへの適応が必要であり、そのための教育やサポート体制を強化することが不可欠です。十分なトレーニングを提供することで、社員が新システムをスムーズに理解し、効果的に活用することができるようになるでしょう。
課題③データ収集の難しさ
データの収集は、DX推進における重要な課題であり、人事DXの成功にも大きな影響を与えます。特に、社員のフィードバックや評価データ、パフォーマンス、エンゲージメント、スキルセットなど、幅広い情報を正確に収集・分析することが必須です。しかし、これらのデータを効率的に収集し、分析可能な形式に統合することは容易ではありません。
社員の基本情報以外のデータ収集には、プライバシーやセキュリティへの配慮が求められ、それに伴う社員の信頼を得ることが重要です。セキュリティ面への懸念が高まる現在、自らの情報を開示する社員の姿勢も慎重になりがちです。そのため、透明性のあるデータ収集プロセスを構築することで、社員の不安を軽減し、協力を得やすくすることが鍵となります。
さらに、データが複数の部署や異なるシステムで分散しているケースでは、これを統合するための課題にも直面します。分散した情報は、企業全体の意思決定のスピードや精度を低下させる要因となり得ます。この問題を克服するには、効率的なデータ収集および分析を可能にする集約的なデータ管理システムの導入や、データ収集プロセスの標準化が重要です。
これらの取り組みによって、人事DXの推進が強化され、企業の競争力を向上させるための基盤が整うといえるでしょう。
成功する人事DXの進め方
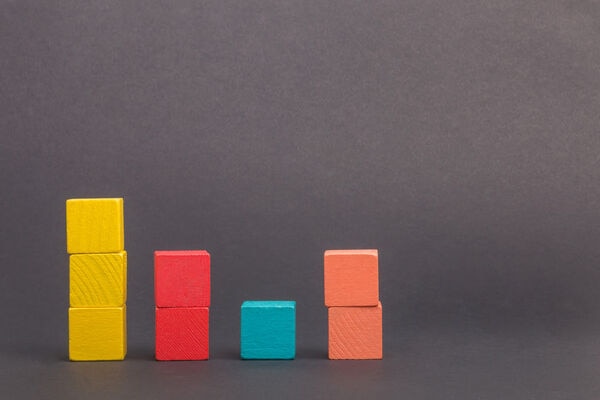
ここでは成功する人事DXの進め方について解説します。
目的と課題の明確化
人事DXの進め方において、まずは目的と課題を明確にすることが不可欠です。何を達成したいのか、そのためにどのような課題が存在するのかを詳細に整理します。具体的な目標を設定することにより、プロジェクトの進行がより明確になります。
たとえば、業務の効率化やエンゲージメントの向上といった具体的な目標があれば、その達成に向けた施策を練ることが容易になります。課題を明確にすることで、克服すべきポイントが浮き彫りになり、次のステップへのアプローチがしやすくなります。
適したツールやシステムの選定
適切なツールやシステムの選定は、成功する人事DXにおいて重要な要素です。市場には多種多様なソリューションが存在し、ニーズに合ったものを選ぶことが求められます。選定プロセスでは、機能性や使いやすさ、費用対効果を考慮し、組織の特性に最適なものを選びます。
さらに、導入後のサポート体制についても確認が必要です。ベンダーが提供する研修やカスタマイズのオプションを活用することで、スムーズな移行を実現します。また、導入後にはシステムの運用状況を定期的に見直し、必要に応じて改善することも重要です。
段階的な導入と評価プロセス
人事DXは段階的に進めることが効果的です。はじめに、小規模な試行を行い、実際の効果を確認します。これにより、問題点を早期に特定し、改善が可能となります。
また、導入したシステムや施策については、定期的に評価を行うことが大切です。効果を測定し、期待した成果に繋がっているかを確認します。この評価を基に、必要に応じて計画を調整し、持続的な改善を図りましょう。
人事DXのポイント

ここでは人事のDX化でおさえておきたいポイントについてみていきましょう。
ポイント①全社的なDX推進の一環として進める
人事のDX化は、企業全体のDX推進の流れの中で進めるべきです。人事部門だけの取り組みではなく、経営層やIT部門と連携しながら、全体のビジョンを共有することが重要です。このようなアプローチにより、各部署間での情報共有が促進され、より一体感のある施策が生まれます。
具体的な例として、経営方針に基づいた人材戦略の策定が挙げられます。人事施策が企業戦略に沿った形で推進されることで、組織全体のレベルアップが促進されます。全社的な視点で進めることで、各部門の協力が得やすくなります。
ポイント②成果を重視した導入設計
人事DXを推進する際には、成果を重視した導入設計が求められます。具体的な目標を設定し、その達成度を測定することで、効果的な施策を打ち出すための基盤をつくります。成果を明確に定義することで、プロジェクトの進捗を評価しやすくなります。
また、導入したシステムや施策についての成果を数字で示し、関係者の納得を得ることが重要です。データに基づく意思決定は、定量的な根拠をもつため、後に続く施策の信頼性を高める効果も期待できます。これにより、社内でのDXへの理解が深まります。
ポイント③社員との協力体制の構築
人事DXの成功には、社員との協力体制を築くことが欠かせません。社員が自らの意見やフィードバックを反映できる環境を整え、積極的に参加できる仕組みを構築することが大切です。これにより、社員が自発的にDXに関与する姿勢が育まれます。
具体的には、研修やワークショップを通じてDXに関連する知識を共有し、全社員の意識を高める取り組みが有効です。また、社員がもつ独自の視点や経験を活かすことで、より効果的な人事施策の創出に繋がります。
人事DXが成功した企業の事例

ここでは、人事DXを推し進めている会社の成功事例をご紹介します。
ユニリーバ
消費財メーカーのユニリーバでは、従来の面接重視の採用スタイルを見直し、ビデオ面接とゲーム型アセスメントを活用した採用手法を導入しました。AIを活用し応募者の適性を解析することで、選考プロセスの公平性とスピードを高めています。
採用コストの削減、適材適所の人材配置による社員の定着率向上などの成果をあげています。
アクセンチュア
コンサルティング大手のアクセンチュアは、AIを活用した採用プロセスの自動化や、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による労務手続きの効率化に取り組んでいます。採用ではAIチャットボットにより候補者の一次対応を行い、人事担当者は面接やオファー段階の質を高めることに集中できるようになりました。 採用担当の工数削減、応募者の満足度向上などの成果をあげています。
日本IBM
情報システムに関わる製品やサービスの提供、企業向けITコンサルティング、システム導入・運用を行っている日本IBMでは、社員のスキルデータ・パフォーマンス・業務履歴などをAIで解析し、離職リスク予測やキャリアパスの提案を行っています。離職率低減、社員エンゲージメントの向上や、AIによるデータドリブンなタレントマネジメントで、リーダー候補や専門人材の早期発掘を実現しています。
サントリー
洋酒、ビール、清涼飲料水の製造・販売等を行うサントリーでは、社員アンケートや日々の業務データを統合して可視化し、部門ごとにエンゲージメントやストレスレベルを把握しています。
また、eラーニングやデジタルワークショップを活用し、集合研修に頼らない学習環境を整備しました。
組織改善の打ち手を迅速に検討できるようになり、離職率や生産性に関するデータが改善しました。
また、オンライン学習導入で、時間や場所の制約を受けにくい育成体制を確立しました。
各社とも、採用プロセスの効率化や社員データの可視化、オンライン学習/コミュニケーション基盤の強化など、人事DXを多方面から推進しています。さらに近年では、データドリブンなアプローチ(AI解析やタレントマネジメントシステム)と、社員が自発的に学習できる仕組み・社内文化づくりを同時に進めるケースが増えています。
効果的・効率的に人事DXを行いたい担当者様は「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」は、人事DXに活用することができます。
自社で作成した教材を簡単に搭載できるため、オリジナリティの高い教育教材の作成が可能です。
さらに、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただけば、さまざまな対象にあわせた社内教育がすぐに実施できます。
「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートすることができます。
コンテンツには、新入社員向けのものや内定者教育向け、管理職向けなどを含む、100本を超える動画と、理解度を測定することができるビジネス問題が3,000問以上揃っております。
ぜひ「サクテス学びホーダイ」をご活用ください。
SAKU-SAKU Testingは、教育担当者様の声を反映したUIデザインで、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を主催する側・新入社員側、いずれも効率的に利用できます。
ご興味がおありの場合は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。