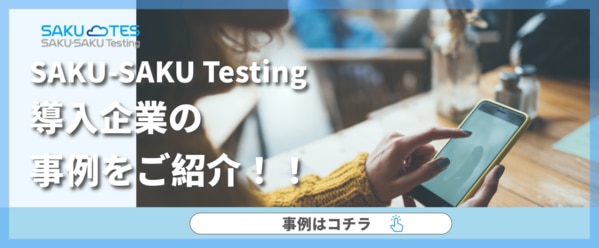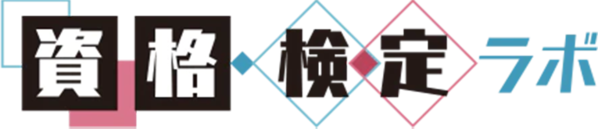面白い研修ゲームで参加率アップ!メリット・成功のコツ・厳選ゲーム例
研修を成功させるカギは「楽しさ」にあります。どれだけ有益な研修でも、
面白くないと身が入らない——。
そんな経験、誰にでもありますよね?
内容がいくら優れていても、退屈なムードでは参加者の集中力は続かず、学びもなかなか定着しません。そこで注目されているのが「研修ゲーム」です。
ゲームの要素を取り入れれば楽しみながら学び、実践的なスキルを自然と身につけることができます。
本記事では、目的別に活用できる「面白い研修ゲーム」を厳選してご紹介します。
目次[非表示]
- 1.研修ゲームのメリット
- 2.代表的なゲーム例
- 2.1.アイスブレイク向けゲーム
- 2.1.1.① 共通点探しゲーム
- 2.1.2.② 吹き出し言葉入れゲーム
- 2.1.3.③ 宝探しゲーム
- 2.1.4.④ 脱出ゲーム(自己紹介型)
- 2.2.チームワーク向けゲーム
- 2.2.1.⑤ グッドアンドニュー
- 2.2.2.⑥ メンバーの取扱説明書
- 2.3.問題解決力向上向けゲーム
- 2.3.1.⑦ NASAゲーム
- 2.3.2.⑧ マーダーミステリー
- 2.4.運動系ゲーム
- 2.4.1.⑨ チャンバラ合戦
- 2.4.2.⑩ ボール回しゲーム
- 3.研修ゲームを成功させる3つのコツ
- 3.1.① 目的を明確にする
- 3.2.② 研修後の振り返りを大切に
- 3.3.③ 誰でも楽しめる環境を整える
- 4.まとめ
研修ゲームのメリット

研修ゲームは、参加者が体験しながら学べるアクティビティ型の研修手法です。
ゲーム形式にすることで自然と主体性が引き出され、学びに対する姿勢も前向きになります。ここでは、研修にゲームを取り入れることで得られる3つのメリットをご紹介します。
メリット① 主体性が高まる
ゲーム形式の研修では、受け身になりがちな参加者も自然と前のめりになります。楽しさや達成感を感じながら取り組めるため、「やらされ感」が減り、主体的な学びが促進されます。
ゲームの考え方やデザインを取り入れてポジティブな変化を生み出す「ゲーミフィケーション」の要素を活用することで、モチベーションが高まり、自ら考えて動く姿勢が引き出されます。
メリット② 内容の定着率が向上する
ゲームでは実際に手や頭を使って学ぶため、知識が「体験」として記憶に残ります。
特にシミュレーション型のゲームでは、実務を模した状況で判断や行動を繰り返すことで、理論だけでなく実践力も養うことができます。こうした試行錯誤のプロセスを通じて、理解が深まり、スキルの定着にもつながります。
メリット③ チームワークやコミュニケーションが活性化する
ゲームには協力や対話が不可欠です。
初対面の社員同士でも自然と会話が生まれ、心理的な距離が縮まることも大きな魅力のひとつです。グループでの目標達成を通じて、役割分担やサポートの意識も育まれ、研修後の業務にも良い影響を与えます。
代表的なゲーム例

ここからは目的に応じたゲームの内容をご紹介していきましょう。
アイスブレイク向けゲーム
研修を始める前の空気が重いと、その後の学びにも影響します。そんなときに効果的なのが「アイスブレイク」です。ここでは、自己紹介や交流のきっかけとして使える、準備が簡単なアイスブレイクゲームを厳選してご紹介します。
① 共通点探しゲーム
3~4人のチームに分かれ、自己紹介をしたうえでチーム全員の共通点を探します。最もユニークな共通点を発表したチームが優勝。お互いを深く知るきっかけになるだけでなく、笑いや驚きが生まれやすく、初対面のメンバー同士でも自然と打ち解けられる人気のアイスブレイクです。
② 吹き出し言葉入れゲーム
写真やイラストの吹き出しに、ぴったりのセリフを考えるシンプルなゲームです。ユニークな発想や笑いを引き出しやすく、場の空気が一気に和やかになります。正解がないことも特徴的で、誰でも気軽に参加できます。
③ 宝探しゲーム
参加者が書いたカード(趣味や得意分野など)を会場に隠し、他の人が探してその内容について質問します。探す・聞くという行動を通じて自然な対話が生まれ、相手への理解が深まります。受け身になりがちな自己紹介も、ゲーム要素を加えることで能動的な交流になります。
④ 脱出ゲーム(自己紹介型)
チームで簡単な謎解きに挑戦しながら、メンバーの得意分野や考え方を活かす仕掛けがある自己紹介型の脱出ゲームです。協力して課題に取り組む中で自然と会話が生まれ、それぞれの個性や長所が浮かび上がります。チームワークと人となりの理解を同時に深められる優れたアイスブレイクです。
チームワーク向けゲーム
チームでひとつの目標に向かい協力する力は、どの職場でも欠かせない要素です。ここでは、自然とチームワークが高まり、関係性の質を深められる研修ゲームをご紹介します。
⑤ グッドアンドニュー
参加者が最近あった「良いこと」と「新しいこと」を1人1分ずつ話していくゲームです。仕事や日常の出来事を共有することで、お互いの価値観や関心を知るきっかけに。短時間で実施でき、前向きな空気が自然に生まれます。心理的安全性の醸成にも効果的です。
⑥ メンバーの取扱説明書
チームメンバーを商品に見立て、「特技」「してほしい頼み方」「NGな対応」などを記載した取扱説明書を作成。お互いの特徴を共有し合うことで、関係性が深まり、日常の業務でも円滑なコミュニケーションが取りやすくなります。
問題解決力向上向けゲーム
ビジネスの現場では、論理的に考え、最適な解決策を導き出す力が求められます。ここでは、楽しみながら問題解決力を育めるゲームをご紹介します。
⑦ NASAゲーム
限られた資源の中で最善の選択を迫られる「宇宙船の不時着」という設定のもと、15個のアイテムに優先順位をつけていくコンセンサス型ゲームです。正解がひとつではない中で、チーム全員の意見を擦り合わせながら、論理的に判断を下していくプロセスが問われます。問題解決力だけでなく、合意形成力や説明力のトレーニングにも最適です。
⑧ マーダーミステリー
物語の登場人物になりきって事件の謎を解く体験型推理ゲームです。限られた手がかりをもとに、他の参加者と情報交換や議論を重ねながら、真相に迫ります。ロジカルに情報を整理し、自分の視点を持って仮説を立て、最終的に説得力ある結論へ導くプロセスは、問題解決力・論理的思考力を向上させるのにぴったりです。
運動系ゲーム
体を動かすアクティビティは、チームの一体感やリフレッシュ効果を高めます。ここでは、楽しさと学びを両立できる、チームビルディングに効果的な運動系ゲームをご紹介します。
⑨ チャンバラ合戦
スポンジの刀を使って腕につけた命(ボール)を落とし合う、大人向けの安全な戦略型アクティビティです。単なる運動ではなく、チームでの作戦会議→実行→振り返りの流れを通して、戦略思考や改善力、チームワークを体感的に学べます。体を動かしながら、楽しさと実務感覚を両立できる点が魅力です。
⑩ ボール回しゲーム
サークル状に並び、ルールに沿ってボールをできるだけ早く回すゲームです。タイムを測定しながら、チームで「どうすれば速くできるか」を話し合い、PDCAサイクルを自然と体験できます。シンプルなルールながら、協力・改善・目標達成の意識を高める優秀な運動系アクティビティです。
研修のネタについてはこちらの記事でも解説していますので、是非参考にしてください。
↓↓↓
社内研修の面白いネタ17選!テーマを決めるときのポイントもご紹介
コンプライアンス研修のネタに関しては、こちらの記事をご参考にしてください。
↓↓↓
コンプライアンス研修のネタ6選!ネタ探しの方法とコンプラ違反を防ぐポイント
研修ゲームを成功させる3つのコツ

研修ゲームを効果的に活用するには、ただ実施するだけでは不十分です。目的に合った設計や振り返りの工夫、安心して参加できる環境づくりが成功のカギとなります。
① 目的を明確にする
「とにかく面白そうだから」と選ぶのではなく、まずは研修の目的をはっきりさせましょう。チームワークを深めたいのか、問題解決力を鍛えたいのかによって、適したゲームは異なります。人数や時間配分にも配慮し、目的に合ったゲームを選ぶことで、単なる「楽しい時間」で終わらず、実りある学びにつながります。
② 研修後の振り返りを大切に
研修ゲームの効果をしっかり定着させるには、「やって終わり」にせず、振り返りの時間を設けることです。体験を通じて得た気づきや学びを、実務にどう活かすかを考えることで、行動変容につながります。
個人での内省に加え、グループで意見を共有、さらに定期的なアンケートやヒアリングを行って具体的な変化を把握していきます。その気づきを、次のアクションプランにつなげていきましょう。
③ 誰でも楽しめる環境を整える
研修ゲームは「楽しさ」が魅力ですが、全員が安心して参加できることが前提です。なかにはゲームが苦手な人や、人前で話すのが苦手な人もいるでしょう。そうした人に配慮し、ルールを丁寧に説明したり、バランスの取れたチーム分けを行ったりすることが大切です。
心理的安全性のある場をつくることで、学びへの前向きな姿勢が自然と引き出されます。
まとめ
どんな研修も、少しの工夫でぐっと効果が変わります。
「面白さ」は学びの原動力です。参加者の笑顔と成長を引き出す第一歩として、ぜひ研修ゲームを取り入れてみてください。
また、社内研修で最も重要なことは「やりっぱなし」で終わらせないことです。研修中は全体のモチベーションが上がったようにみえても、終了後に士気が下がってしまうケースは少なくありません。
社内研修を実施すること自体が目的になってしまっては、社員のためにならないだけでなく、研修にかけた時間やコストも無駄になってしまいます。
社内研修の企画担当者は、会社の課題に合った、本質的にやるべき研修は何かを考えることが大切です。そのためには、研修後にテストを行うなどして、社員研修で伝えたかったことが浸透しているかを確認し、社員研修の効果を測定することが有効です。
社員研修の効果測定なら、企業の研修や通信教育などのシステム運用における20年以上の実績をもつイー・コミュニケーションズのeラーニングプラットフォームSAKU-SAKU Testingがおすすめです。
「SAKU-SAKU Testing」は自社で作成した教材を搭載して利用できるので、教育プラットフォームとして活用することが可能です。
また、自社コンテンツを搭載するeラーニングプラットフォームとしての利用以外に、あらかじめ社員教育に必要な教材がパッケージ化されている「サクテス学びホーダイ」など、さまざまなニーズに対応したeラーニングのご提案が可能です。
ご興味がおありの場合はお気軽にお問い合わせください。