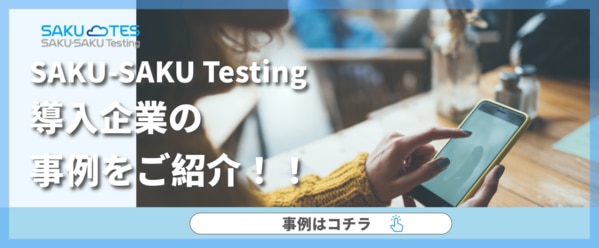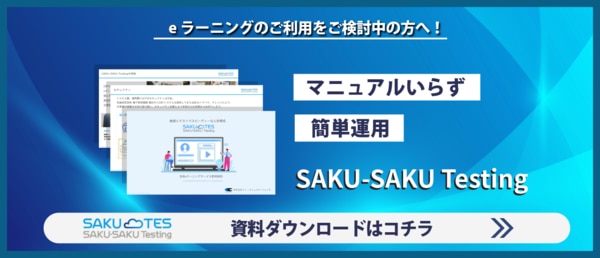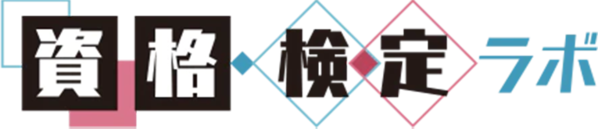研修スケジュールの立て方|手順やポイントをわかりやすく解説
企業が研修を効果的に行うためには、明確かつ計画的なスケジュールを立てることが重要です。適切なスケジュール設計は、受講者が学びやすい環境を整えるだけでなく、学習意欲を高め、実践的なスキルの習得に繋がります。
本記事では、研修スケジュールを効率的に作成するための具体的な手順やポイントについて解説します。
目次[非表示]
- 1.研修スケジュールを作成する手順
- 1.1.手順①研修の目的や着地点を明確にする
- 1.2.手順②研修予算を設定する
- 1.3.手順③研修カリキュラムを決定する
- 1.4.手順④講師や関係者の日程を調整する
- 1.5.手順⑤スケジュール表に組み込む
- 2.研修スケジュールの作成ポイント
- 2.1.ポイント①1日に詰め込みすぎないスケジュール設計
- 2.2.ポイント②研修の対象者や内容を明確に設定する
- 2.3.ポイント③適切な休憩時間を確保する
- 2.4.ポイント④研修後の振り返り時間を準備する
- 2.5.ポイント⑤座学だけでなく実践形式も取り入れる
- 3.研修スケジュールの具体例
- 3.1.新入社員研修スケジュールの事例
- 3.2.1日研修のスケジュール例
- 3.3.OJT研修スケジュールの例
- 4.効果的な研修スケジュールの進め方
- 4.1.事前に研修内容を関係者と共有する
- 4.2.研修進行中のフィードバックを行う
- 4.3.研修終了後の評価と改善点の確認
- 5.研修スケジュール立案の注意点
- 5.1.予定変更時の柔軟な対応を考慮する
- 5.2.社内外の連携を効率化する方法
- 5.3.スケジュール管理に優れたシステムの導入
- 6.社員研修にぜひeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
研修スケジュールを作成する手順

まずは研修スケジュールを作成する手順についてみていきましょう。
手順①研修の目的や着地点を明確にする
研修を成功に導くためには、まずその目的を明確に設定することが必要です。何を学び、どのような成果を期待するのかを明確にすることで、研修の方向性が決まります。例えば、ビジネスマナー研修の場合、基本的なマナーとその実践を目指すのか、より高度なコミュニケーションスキルの向上を狙うのかで内容は大きく異なります。この段階で受講者に期待する成果を示すことで、受講者のモチベーションを高めることにもつながります。
手順②研修予算を設定する
研修を無事に実施するためには、予算設定が欠かせません。社内研修の場合も外部講師を招く場合も、行うためにはコストが発生します。予算を決める際には、参加人数や研修の内容、講師の選定にかかる費用などを考慮する必要があります。また、可能な限り多くの選択肢を検討し、良いコストパフォーマンスを実現するための情報を調査しておくことが重要です。
手順③研修カリキュラムを決定する
研修カリキュラムは、受講者が何を学ぶかの具体的な計画を示します。そのため、対象者のニーズを把握し、どのスキルや知識が必要なのかを考えることが求められます。例えば、新入社員向け研修ではビジネスマナーや会社の理念、業務の流れなどが重点的に扱われることが一般的です。また、カリキュラムには座学だけでなく、実践的な演習やグループディスカッションなども取り入れることで、より深い学びを促すことができるでしょう。
手順④講師や関係者の日程を調整する
研修を実施するにあたって、講師や関係者の日程調整は欠かせない作業です。講師の専門性や都合によって、実施日が限られることも多いです。したがって、候補日をいくつかピックアップし、講師と受講者のスケジュールを照らし合わせて最適な日を選定する必要があります。また、予め調整された情報を関係者に報告し、円滑に進められるようにコミュニケーションをとることも重要です。
手順⑤スケジュール表に組み込む
全ての準備が整ったら、研修スケジュールを表に落とし込みます。スケジュール表には、各セッションの時間や内容、担当講師の情報をしっかりと記載し、受講者が一目で把握できるようにすることが大切です。見やすいフォーマットを用いると、受講者は自分の役割やタイミングを把握しやすくなります。さらに、スケジュールに余裕をもたせることで、予定外の変更にも対応できる柔軟性をもたせることが可能となります。
研修スケジュールの作成ポイント

ここでは研修スケジュール作成におさえておきたいポイントについて解説します。
ポイント①1日に詰め込みすぎないスケジュール設計
研修が充実している一方で、受講者が疲労困ぱいになってしまうこともあります。特に、新しい情報を一度に多く詰め込んだ場合、受講者が情報を消化しきれず、理解が浅くなる可能性があります。このため、適度なスケジュールを設定し、各セッションの合間には時間を設けて休息を取らせることが重要です。無理に一日ですべてを学ぼうとするのではなく、研修を数日に分けることも選択肢の一つです。また、各日のテーマを明確に分けることで、受講者は特定の知識に集中しやすくなるメリットもあります。
ポイント②研修の対象者や内容を明確に設定する
受講者に応じた研修内容の設定はとても大切です。研修の目的に応じて、どのような知識やスキルが必要とされるかを事前に調査しておくと、効果的なプログラムが組めます。新入社員と中堅社員では求められるスキルが異なるため、それぞれのレベルに応じたカリキュラムを用意することが求められます。これによって、受講者は自分の成長に合わせた学びを体験しやすくなります。
ポイント③適切な休憩時間を確保する
研修中の休憩は不可欠です。受講者が集中力を取り戻し、効果的に情報を吸収するためには、適切なタイミングでの休憩が必要です。例えば、長時間のセッションの場合、50分学んで10分休むといったスパンを設けると良いでしょう。特に疲労が蓄積しやすい午後には、積極的に休憩を挟むことが重要です。休憩時間には軽食を提供することで、エネルギーを補充し、再度の学びに備えることができます。また、リラックスできる環境を整えてあげることで、研修の充実度もさらに向上する可能性があります。
ポイント④研修後の振り返り時間を準備する
研修終了後には、振り返りの時間を設けるべきです。この時間は、受講者が学んだ内容を整理し、実際の業務での応用を考える良い機会になります。手元のノートや資料を見ながら、自分なりに重要なポイントをまとめ直すことができ、理解が深まります。さらに、振り返りをグループディスカッションの形式で行うと、異なる視点からの意見を取り入れることができ、学びの広がりをもたらします。自己反省と他者からのフィードバックが組み合わさることで、学習効果が高まります。
ポイント⑤座学だけでなく実践形式も取り入れる
研修のスタイルを多様化することは、受講者の関心を引き、学びを定着させる上で重要です。特に、理論だけでなく実践形式のアクティビティを組み込むことで、知識がより深く身につくことが期待できます。ロールプレイやグループワーク、ケーススタディなどの実践的な活動を取り入れることで、受講者は実際の業務に即した感覚を体験できます。また、講義だけでは得られない経験を通じて、受講者が自発的に考え、行動する力を育むことが可能となります。学んだ内容をすぐに試してみる環境が整っていると、受講者の自己成長にもつながります。
研修スケジュールの具体例

では、研修スケジュールの具体例についてみていきましょう。
新入社員研修スケジュールの事例
新入社員研修は、会社に新しい仲間を迎える大切なイベントです。多くの場合、期間は 1~2 週間です。大まかな流れは以下のとおりです。
1週目:会社を知る
日 |
主な内容 |
1日目 |
オリエンテーション(研修の目的・進め方の説明) |
2日目 |
各部署の紹介 |
3~4日目 |
ビジネスマナー(挨拶・名刺交換・電話/メール対応など)の習得 |
最終日 |
1週目の振り返り・質疑応答 |
2週目:仕事を体験する
- 実際の業務に近い演習やグループワーク
例)簡単なプロジェクト体験、ロールプレイ
- メンターや先輩社員からのフィードバック
- 週末にはまとめと発表を行い、学んだことを整理
ポイントは以下のとおりです。
-
段階的に進める
まず会社や仕事の全体像を理解し、その後に実践へ移ると効果的です。
-
振り返りの時間を確保
各週の最後に質疑応答や自己評価の時間を設けることで、理解が深まります。
-
実務に近い体験を用意
早い段階で「仕事のイメージ」をつかむと、配属後のギャップが少なくなります。
このように、1週目で土台を作り、2週目で実践に挑戦する2ステップ形式が一般的で、効率よく新人の成長を促せます。
1日研修のスケジュール例
1日の短時間で完結する研修は、特定のテーマに焦点を当てて効率的に進行することが求められます。例えば、ビジネスマナーをテーマにした1日研修では、次のようなスケジュールが考えられます。
【スケジュール例】
09:00-09:30 |
オリエンテーションを行い、受講者の雰囲気を和らげる |
09:30-11:00 |
基本的なビジネスマナーについての講義を実施 |
11:00-11:15 |
小休憩 |
11:15-12:30 |
実践の場としてグループディスカッションやロールプレイを行う |
12:30-13:30 |
昼食 |
13:30-15:00 |
面接時のマナーについての講義を行う |
最後の45分は受講者同士での振り返りを行うことで、学びの定着を図ります。
このように、短い時間でも濃い内容を詰め込むことができます。
OJT研修スケジュールの例
OJT(On-the-Job Training)は、実際の職場で仕事をしながら学ぶ研修です。新入社員が実務を通じて成長できるよう、段階的なスケジュールを組みましょう。
期間 |
内容 |
目的 |
1週目 |
午前:プロジェクト概要の説明と基本操作レクチャー 午後:先輩の指示を受けながら実務を体験 |
仕事の全体像をつかみ、職場の流れに慣れる |
2週目 |
午前:担当業務を自分で進める(責任範囲を拡大) |
自律的に業務を回しつつ、改善点を学ぶ |
成功のポイント
-
段階的に責任を増やす
いきなり全て任せず、まずは小さなタスクから。
-
フィードバックを必ず入れる
毎日または週末にレビュー時間を設け、疑問や課題を解消。
-
学びを可視化する
進捗や気づきを共有シート等にまとめ、成長を実感できるようにする。
この流れで進めると、新入社員は安心して実務に取り組みながら、着実にスキルを伸ばすことができます。
効果的な研修スケジュールの進め方

ここでは効果的な研修スケジュールの進め方についてみていきます。
事前に研修内容を関係者と共有する
研修を円滑に進めるためには、事前に関係者と研修内容を共有することが不可欠です。特に、講師や受講者、さらに上司や人事部門に対して、何を学ぶのか、どのような目的があるのかを明確に伝えることで、全員が同じ方向を向いて研修に参加することが可能になります。
事前に共有された情報は、受講者の不安を軽減する効果もあります。何を達成するための研修なのかが明確であれば、受講者は安心して学びに臨むことができます。さらに、関係者からの意見やアドバイスを統合することで、より実践的な内容にブラッシュアップされることも期待でき、充実した研修を実現できます。
研修進行中のフィードバックを行う
研修が進行している間には、受講者へのフィードバックを行うことが重要です。この段階でのフィードバックは、受講者の理解度や関心を把握するための貴重な手段です。各セッション後に質疑応答の時間を設けたり、簡単なアンケートを行ったりする方法が考えられます。
また、講師も受講者からのリアルタイムでの反応を見極めることで、進行ペースを調整し、必要に応じて内容に柔軟にアプローチできます。こうしたフィードバックによって、受講者は自分の理解度を把握することができ、次のステップへとつながるため、学びの深まりを図れます。
研修終了後の評価と改善点の確認
研修を終えた後には、全体の評価や改善点を確認することが必須です。研修の成果を測定するためには、受講者からのアンケートやフィードバックが非常に有効です。具体的な数値で効果を示すことができるため、今後の研修計画に活かす貴重な資料となります。
また、受講者がどのようなことを学び、どのように日常業務に活かしているかを評価することも大切です。この過程で必要なら、次回の研修企画にフィードバックを採り入れ、改善策を講じておくことが求められます。こうした一連の流れが結果的に次回の研修の質を向上させ、企業全体のスキルや知識の底上げに繋がります。
研修スケジュール立案の注意点

研修スケジュール立案の際には注意点もあるため、みていきましょう。
予定変更時の柔軟な対応を考慮する
研修の実施にあたり、想定外の事態が発生することは避けられません。このため、予定変更に柔軟に対応できる仕組みが必要です。たとえば、受講者が急遽欠席した場合や、講師の都合がつかなくなった場合でも、迅速かつ適切に代替案を用意することで、研修が無駄にならないよう努めることが求められます。
事前に複数の候補日や講師をリストアップしておくことや、代替のプランを考えておくことは非常に有効です。受講者がストレスを感じることなく、スムーズに研修を受けられるよう配慮することは、受講者の学びを深めるためにも重要な要素です。
社内外の連携を効率化する方法
研修を成功させるためには、社内外の連携が欠かせません。社内の各部門、特に人事や関連部署とのコミュニケーションを密にすることで、研修の方向性や目的が一貫性をもつようになります。外部講師を招く場合、事前に内容について打ち合わせを行い、期待する成果を明確に伝えることが肝要です。
また、社外の研修機関や専門家との連携も考慮するべきです。共同での情報共有を通じて、方針やスケジュールを確認し合い、トラブルを未然に防げる状態を作り出すことが効果的です。このような効率的な連携により、円滑な研修運営が実現します。
スケジュール管理に優れたシステムの導入
スケジュール管理を適切に行うためには、専用の管理システムの導入を検討することが重要です。理解しやすいインターフェースをもち、関係者全員がアクセスできるツールを使うことで、情報の透明性が向上し、ミスを減少させられます。
また、システムを活用することで、研修日程の変更や調整を簡単に行えるため、リアルタイムでの更新が可能です。これにより、関係者がいつでも最新の情報を確認でき、柔軟に対応できる環境を作ることができます。加えて、研修に参加する社員からのフィードバックを収集する機能をも備えていると、今後の研修へ向けた改善策を迅速に行うことが可能になります。
社員研修にぜひeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
本記事では、研修を実施する上でスケジュール立ての流れやおさえたいポイントなどをご紹介しました。
イー・コミュニケーションズは研修を実施する際に活用できるeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」やSAKU-SAKU Testingを活用した様々なコンテンツをご用意しております。
「SAKU-SAKU Testing」では、新入社員研修として利用できるコンテンツ「ビジネスベーシック」をご用意しています。
「ビジネスベーシック」では、入社1年目〜3年目までの社会人としての基本を学べる12コースを全45本の動画でご用意しています。
5~15分の動画と確認問題によって、スキマ時間で効率的に知識を定着させることができます。
管理用画面から受講状況やテスト結果が簡単に確認でき、新入社員の受講も簡単に管理ができます。
また、複数のコンテンツがセットされたコンテンツパッケージ「サクテス学びホーダイ」もございます。
サクテス学びホーダイは100本を超える動画と、理解度を測定することができるビジネス問題が3,000問以上登録されています。
また、内定者教育向けのコンテンツから、入社3年目までのビジネススキルをアップさせるコンテンツと、さらに管理職候補から管理職向けのコンテンツが揃っています。
さらに、企業の3大リスクである「コンプライアンス」「ハラスメント」「情報セキュリティ」のコンテンツも入っているため、全従業員向けの教育にもご利用いただけます。
SAKU-SAKU Testingは、教育担当者様の声を反映したUIデザインで、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を主催する側・受講者側、いずれも効率的に利用できます。
ご興味がおありの場合は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。