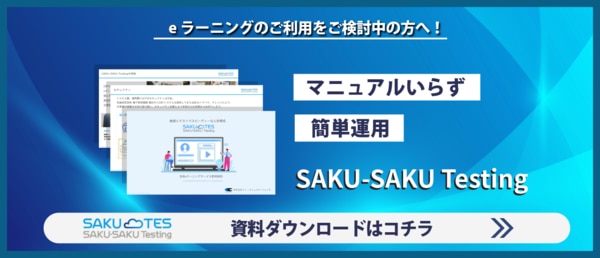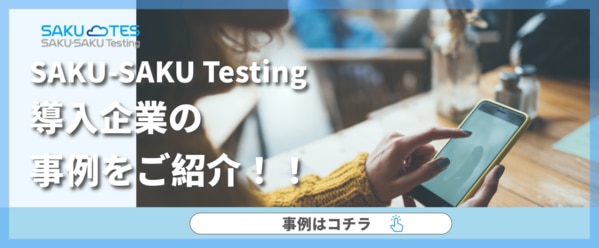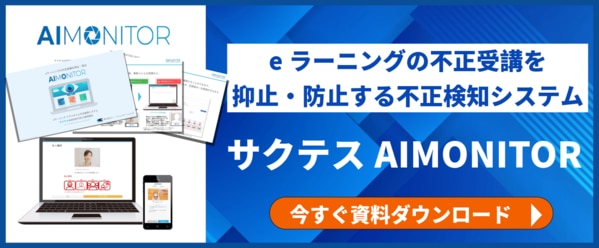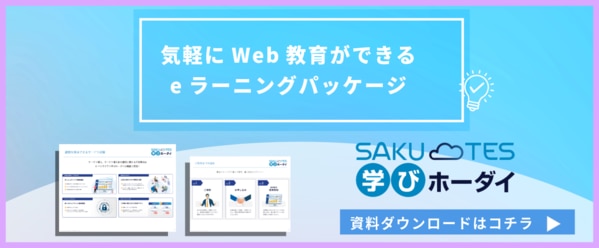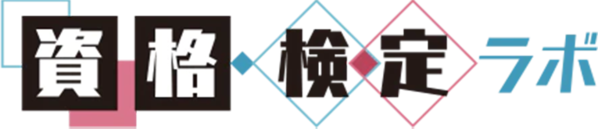エルダー制度とは?新入社員を効果的に育成する方法を解説
従業員の育成を効果的に行う手法のひとつにエルダー制度があります。入社したばかりの新入社員は多くのことを学ばなければならず、この時期の教育がその後の成長に大きな影響を与えます。本記事では、エルダー制度の内容、メリットやデメリット、導入時のポイントを解説します。
目次[非表示]
- 1.エルダー制度の基礎知識
- 2.エルダー制度とメンター制度との違い
- 2.1.メンター制度との違い
- 2.2.フォローの範囲における違い
- 2.3.担当者の役割比較
- 3.エルダー制度が注目される理由
- 3.1.新入社員の早期離職防止への効果
- 3.2.働きやすい職場環境の実現
- 3.3.社員同士のエンゲージメント促進
- 4.エルダー制度のデメリット
- 4.1.エルダーへの負担の増加
- 4.2.新入社員とエルダーの相性問題
- 4.3.エルダー間でのサポートのばらつき
- 4.4.エルダーへの依存のリスク
- 5.エルダー制度の導入手順
- 5.1.導入目的の明確化
- 5.2.エルダーと新入社員の選定
- 5.3.制度実施計画の策定と環境整備
- 6.エルダー制度活用のポイント
- 6.1.全社的な取り組みを意識する
- 6.2.エルダーの教育とサポート体制の確立
- 6.3.効果的なエルダーの選出方法
- 7.エルダー制度の成功事例
- 8.まとめ
- 9.効果的・効率的に社員の育成を行いたい担当者様は「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
エルダー制度の基礎知識

エルダー制度は、新入社員に対するOJT(On-the-Job Training)の一環として、多くの企業で導入されている仕組みです。その他制度との違いや目的について見ていきましょう。
エルダー制度とは
エルダー制度では、数年上の先輩社員が新入社員をサポートし、業務の進め方や社内ルールについて具体的かつ丁寧に指導を行います。この制度は、新入社員が職場において直面する疑問や不安を解消する重要な役割を担っています。実際に、エルダーとの日常的なやり取りを通じて、新入社員は業務に必要な知識やスキルを実践的に学べるだけでなく、職場内の文化や風土に早期に馴染むことが可能になります。
エルダー制度の目的
エルダー制度の主要な目的は、新入社員が職場環境にスムーズに適応できるよう支援することです。この制度では、業務を通じて必要な知識やスキルを向上させることが重視され、新入社員の成長を促進します。さらに、エルダー制度を通じて、新入社員と先輩社員のコミュニケーションの質を高め、職場での信頼関係を築くことが可能となります。このような取り組みによって、新入社員の安心感とやる気が向上し、職務への意欲を引き出すだけでなく、自己成長を目指す姿勢がつちかわれていきます。また、先輩社員からの細やかなサポートにより、新入社員の職場定着率が改善し、企業全体としても早期離職を減少させる効果が期待されます。エルダー制度の目的は、これらの取り組みを通じて組織全体の活力を向上させることにも繋がっています。
エルダー制度とメンター制度との違い

エルダー制度は、新入社員教育において他の育成制度と比べて独自の特徴をもっています。その最大の特長として、OJT(On-the-Job Training)の形式を重視している点が挙げられます。エルダー制度では、先輩社員が直接指導を行い、実務を通じて具体的なスキルを学ぶ機会が提供されるため、教育内容が非常に実践的であることが魅力です。エルダー制度により、新入社員はより安心感をもちながら業務に取り組むことができ、早期戦力化が期待できるのが大きな利点と言えるでしょう。
メンター制度との違い
メンター制度は新入社員に対して精神的なサポートを提供するための仕組みであり、業務面だけでなくメンタル面の相談役として重要な役割を担っています。通常、メンターは他部署の社員が選ばれることが多く、職場内の利害関係やしがらみを避けた形で新入社員が安心して相談できる環境を提供しています。一方で、エルダー制度は同じ部署の年上の先輩が中心となって指導を行う制度です。このエルダー制度では、業務知識や企業文化の共有に重点を置き、新入社員が実務に直結した学びを得られることが特徴となっています。このように、エルダー制度は具体的な実務や企業の運営に深く繋がったサポートを提供する点で、メンター制度との大きな違いが見られます。結果として、エルダー制度は新入社員が効率的に業務に適応し、部署内での役割を迅速に果たすことができるようになるための仕組みとも言えるでしょう。
フォローの範囲における違い
エルダー制度は、新入社員の業務に密着したフォローを特徴とする仕組みです。この制度では、指導者であるエルダーが具体的な業務アドバイスを通じて新入社員の成長を支援し、日常業務を共に行いながら不安の軽減に努めます。一方で、メンター制度は心理的なサポートやキャリア形成を中心に、新入社員が業務以外の悩みについても相談できる幅広い支援を提供する点で特徴があります。そのため、エルダー制度が業務に特化したフォローを行うのに対し、メンター制度は新入社員の心理的サポートやキャリア全般を含めた広範囲な支援にも対応することが大きな違いといえます。
担当者の役割比較
エルダー制度における担当者は、実務を通じて新入社員の教育を直接行う重要な役割を担っています。彼らは新入社員に対して実際の業務の流れを理解させ、必要なスキルを身につけるよう指導する役割を果たします。担当者による迅速なフィードバックを通じて、新入社員の学びの効率を高める効果が期待されます。
一方、メンター制度における担当者は、主に新入社員の心理的なサポートやキャリア形成に関するアドバイスを提供する役割を担っています。この制度では、単なるスキルの伝達だけでなく、新入社員が仕事への取り組み方や、将来的なキャリアパスを考えるための広範な支援を行うことに重点を置いています。そのため、エルダー制度が業務遂行に直結した教育を重視するのに対し、メンター制度は新入社員の全般的な成長や心身のサポートを追求するという違いがあります。
結果として、エルダー制度では業務スキルを中心とした効率的な教育が提供される一方で、メンター制度では新入社員一人ひとりの個人的な成長やキャリア形成が重視されるため、それぞれの制度での担当者の責任や役割には明確な違いがあると言えます。
エルダー制度が注目される理由

エルダー制度は、新入社員の育成の効果的な手法として近年、重要性が増しています。効果やメリットなどを見ていきましょう。
新入社員の早期離職防止への効果
新入社員の早期離職は、人材不足が深刻化している現代の職場における大きな課題の一つです。エルダー制度は、そのような状況への解決策として注目されています。エルダー制度では、先輩社員が新入社員に対して業務をレクチャーしたり一緒に進めたりすることで、新入社員は業務内容の理解を深めるだけでなく、職場の文化や価値観、さらには人間関係にもスムーズに馴染むことが可能となります。さらに、この制度により、新入社員が疑問や不安を感じた際にすぐ相談できる環境が構築されるため、安心感を得られる点も大きな特徴です。このようにして、エルダー制度は新入社員の職場適応をサポートし、早期離職のリスク低減に寄与します。
働きやすい職場環境の実現
エルダー制度は、新入社員だけでなく職場全体の環境改善に寄与する重要な仕組みです。この制度を通じて、新人が適切な指導を受け成長する過程で、先輩社員もマネジメントスキルやコミュニケーション能力を強化できます。これにより、個人の能力向上だけでなく、チームの連携力が向上し、効率的で働きやすい職場環境が作り上げられます。また、職場内でオープンなコミュニケーションが促進されることで、社員間の信頼関係が深まり、職場の円滑な運営にもつながります。結果として、離職率の低下や職場全体の活気向上が期待され、エルダー制度を有効活用することが、持続性とチームワークを両立した職場を築くためのカギとなります。
社員同士のエンゲージメント促進
社員同士が積極的に関わり合える環境をつくることは、エルダー制度の大きなメリットの一つです。新入社員はエルダーとの関わりを通じて、他の社員とも積極的にコミュニケーションを図る機会を得られるため、職場全体の雰囲気が向上します。このような相互作用が生まれることで、職場は協力しやすい環境になり、社員一人ひとりが職務に対する達成感や満足感を得られるようになります。さらに、エルダー制度を活用することで、社員間の結束力が強まり、組織全体がより活性化される効果も期待できます。このようなポジティブな循環は、働きやすい職場環境を形成する重要な要素と言えるでしょう。
エルダー制度のデメリット

エルダー制度には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。具体的に見ていきましょう。
エルダーへの負担の増加
エルダー制度のデメリットの一つは、エルダーの役割が増加することで負担が大きくなる点です。新入社員を教育するためには多くの時間とエネルギーが必要であり、日常業務に加えて指導を行うことで業務負荷がさらに増加する可能性があります。その結果、エルダー自身の業務に影響が出たり、効率が低下したりすることがあります。また、長期的にこうした過剰な負担が続くと、エルダーにストレスが蓄積し、モチベーションの低下や最悪の場合は離職につながるリスクも考えられます。エルダー制度のこうしたデメリットを考慮し、エルダーの負担を軽減するためのサポート体制の整備が非常に重要です。
新入社員とエルダーの相性問題
新入社員とエルダーの相性問題は、エルダー制度における代表的なデメリットの一つといえます。エルダーとの関係性が良好であれば、新入社員の成長を促進し、教育効果を高めることが期待できます。しかし、相性が悪い場合、指導が円滑に機能しないことがあり、この相性の不一致は新入社員が孤立感を抱えたり、精神的にストレスを感じる要因となり得ます。特に、性格やコミュニケーションスタイルの違いによって指導方法が適切に伝わらない場合、新入社員が必要なスキルや知識を十分に身につけられないリスクも存在します。このようなデメリットを最小限に抑えるためには、適切なエルダーの選定やサポート体制の見直しが重要となります。
エルダー間でのサポートのばらつき
エルダー制度においては、エルダー間でのサポートのばらつきがデメリットとして挙げられます。各エルダーがもつ経験やスキル、指導スタイルには個人差があるため、新入社員への教育が一貫性を欠くことがあります。このようなバラツキのある教育体制は、新入社員の成長速度や習得内容に影響を与え、場合によっては全体的な職場のパフォーマンス低下を招く可能性もあります。さらに、サポートの質がエルダーごとに異なることで、新入社員自身が不満を抱きやすくなり、社員間での摩擦や信頼低下に繋がる懸念もあります。これらの課題は、職場の雰囲気を悪化させたり、働く人の意欲を下げたりする可能性があるため、エルダー制度の導入・運用にあたっては、適切な対応策を準備しておくことが不可欠です。
エルダーへの依存のリスク
エルダー制度のデメリットの一つとして挙げられるのが、エルダーへの過度な依存です。新入社員がエルダーを頼りすぎると、自分で問題を解決する力が育たず、結果として独力で業務を遂行する能力が欠如してしまうリスクがあります。この状況が長引くと、エルダーがいない場面で新入社員が適切に対応できなくなる可能性も出てきます。そのため、エルダー制度を運用する際には、あくまでエルダーが補助的なサポート役であることを明確にし、新入社員が主体性をもって成長できる環境を整えることが重要です。信頼関係を築くことは大切ですが、それ以上に自立心を育むためのバランスを意識したサポートが求められます。
エルダー制度の導入手順

エルダー制度を効果的に導入するためには、いくつかの重要な手順を踏む必要があります。具体的な手順を説明します。
導入目的の明確化
エルダー制度を効果的に導入するためには、その目的を明確にすることが重要です。企業はまず、その人材育成における具体的なニーズを丁寧に洗い出し、その結果に基づいた目的設定を行う必要があります。たとえば、新入社員が職場環境にスムーズに適応し、早期に戦力となるようなサポートを目的とした教育を行うことや、社員同士のコミュニケーションを活性化させる取り組みが考えられます。このようにエルダー制度の目的をはっきりさせることで、制度運営の方向性が定まり、効率的かつ成果につながる戦略を構築しやすくなります。さらに、導入目的が明確であれば、制度を通じて得られる期待効果を社員全体に共有しやすくなり、それが参加意欲や制度の成功に寄与するというメリットもあります。
エルダーと新入社員の選定
次に、エルダーと新入社員の選定を行う際には、エルダー制度に基づいた適切な人選が求められます。エルダーは新入社員に直接指導を行う重要な役割を担うため、その選定基準が非常に重要です。エルダーとしては、ただ経験が豊富であるだけでなく、指導力やコミュニケーション能力を兼ね備えた人物が適しています。一方で、新入社員を選定する際には、実際の業務内容や所属チームとの相性を見極めることが必要です。このプロセスを通じて、エルダー制度の目的である効果的な指導とスムーズな職場適応を実現することが可能となります。
制度実施計画の策定と環境整備
最後に、エルダー制度の実施計画の策定と必要な環境整備を行うことが不可欠です。エルダー制度を効果的に運用するためには、具体的な運用方法とスケジュールを明確にし、新入社員との関係が円滑に進むよう計画的に整備を進めていく必要があります。制度の成否は、どのような人をエルダーに選ぶかにかかっていると言っても過言ではありません。また、エルダーが新入社員を適切にフォローアップできる環境を整えることも欠かせません。その一環として、オープンなコミュニケーションを促進する共有スペースの設置や、進捗状況について話し合える定期的なフィードバックの場を設けることが重要です。このような取り組みを通じて、エルダー制度の効果を最大限に発揮し、新入社員が安心して成長できる職場環境を築いていきます。
エルダー制度活用のポイント
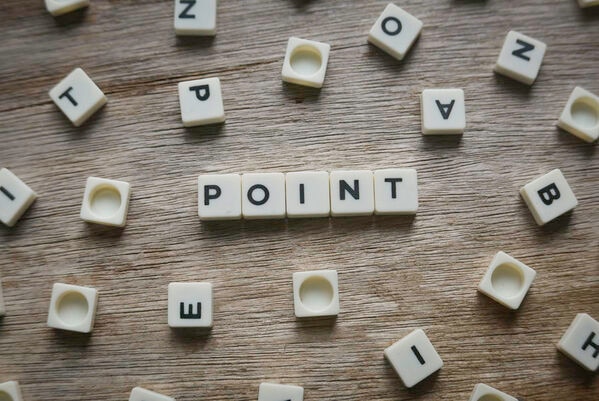
エルダー制度を有効に活用するためのポイントは、いくつかの重要な視点から成り立っています。まず、全社的な取り組みを意識することが不可欠です。この制度を導入することで、企業全体の人材育成の一環として位置付ける必要があります。この際、エルダー制度は単なる短期的な施策ではなく、長期的な人材育成戦略の中で重要な役割を果たすものとして考えられるべきです。各部署がエルダー制度の重要性を理解し、一貫した方針で取り組むことで、制度の成功へと繋がります。
さらに、一部の部署だけではなく、全社規模で取り組みを拡大することが重要です。これにより、エルダー制度の活用範囲が広がり、各部署間での連携や共有が進み、より効果的な人材育成が実現するでしょう。このように、エルダー制度を最大限に活用するには、企業全体での協力体制や制度の理解を深める働きかけが欠かせません。
全社的な取り組みを意識する
全社的な取り組みを促進するには、経営層からの強力なサポートが欠かせません。経営陣がエルダー制度の目的を深く理解し、その重要性を各部署のリーダーにしっかり伝えることで、この制度をより多くの社員に周知させることが可能になります。それに加え、社内でエルダー制度の成功事例や具体的な成果を共有することは、社員一人ひとりの参加意欲を高める上で非常に効果的です。こうした仕組みを通じて、エルダー制度が社員自身のスキル向上やキャリア成長にも寄与するという価値を実感できる環境を構築することが重要です。これらの取り組みが全社的な協力体制を形成し、持続可能な制度の基盤を支える鍵となります。
エルダーの教育とサポート体制の確立
適切な指導を行うためには、エルダーに対する教育プログラムを整えることが重要です。エルダー制度が効果的に機能するためには、エルダー自身が指導の役割を果たせるよう、専門的なスキルや知識を備える必要があります。そのため、定期的な研修やワークショップを実施し、指導方法やコミュニケーションスキルを向上させる機会を提供することが求められます。さらに、この制度をより強化するためには、エルダー同士が情報を共有し、互いに意見を交換できる環境を整えることも非常に重要です。このような交流の場は、相互のサポート体制を確立する助けとなるだけでなく、エルダーの成長を促進し制度全体の質を向上させる効果が見込まれます。結果として、エルダー制度が円滑に運用され、より効果的な教育とサポートが可能となります。
効果的なエルダーの選出方法
制度の成否は、どのような人をエルダーに選ぶかにかかっていると言っても過言ではありません。エルダーには新入社員との円滑なコミュニケーションを築き、知識や経験を的確に伝える能力が求められます。そのため、業務内容への深い理解をもつことはもちろん、人間性や教育スキルといった要素を選定基準に含めることが重要です。さらに、エルダー制度をより効果的に活用するためには、候補者の過去の指導経験や社員間でのコミュニケーションスタイルを考慮した上で評価することが推奨されます。また、エルダー制度の成功を支えるためには、エルダーとしての適性を見極める面談プロセスや評価制度を整えることも欠かせない要素となります。これにより、新入社員の成長を促し、エルダー制度の目指す成果を最大化することが期待できます。
エルダー制度の成功事例

エルダー制度を導入し成功を収めている企業は多く、その事例はさまざまな業界で広がりを見せています。これらの成功事例では、企業文化の改善や社員の定着率向上が注目されており、制度の効果が明確に示されています。具体的に成功企業の事例を紹介します。
ソフトバンク
ソフトバンクでは、エルダー制度を効果的に活用し、新入社員の職場適応を支援するためのシステムがあります。ソフトバンクのエルダー制度では、経験豊富な先輩社員が新入社員の教育やサポートを担当することで、新入社員が安心して業務を習得できる環境を提供しています。その結果、新入社員の職場適応がスムーズになり、社員全体のモチベーション向上にも貢献しました。この事例は、エルダー制度が適切に運用されることで企業全体の成長に貢献するよい例と言えます。
参考:https://www.softbank.jp/recruit/graduate/crosstalk/developmentofnewpeople/
トヨタ自動車
トヨタ自動車では、エルダー制度とは違う名称で「職場先輩制度」という制度を導入し、新入社員の育成に注力しています。この制度は、2、3年上の先輩が仕事内容や職場のルールなどを新入社員を直接指導する仕組みです。この取り組みにより、コミュニケーションが円滑に進み、業務内容への理解が深まるだけでなく、現場で求められるスキルの習得がスムーズに進むことが可能となっています。
参考:https://www.toyota-recruit.com/saiyo/environment/train/
大和ハウス工業
大和ハウス工業も「OJTエルダー制度」という名称でエルダー制度を導入しています。新入社員の実務だけでなく、人間力の成長も支援することを目的とし、新入社員の早期戦力化とともにエルダーとして任命された社員が縦横連携を取りながら中心となって指導にあたるためエルダー側の成長も期待されています。
参考:https://www.daiwahouse.co.jp/recruit/traning/index.html
まとめ

エルダー制度は、新入社員の育成を支援する有効な手法として、多くの企業で採用されています。この制度では、先輩社員が新入社員に対して直接指導を行い、単なる業務スキルの習得にとどまらず、職場の文化や人間関係への適応も支援します。これにより、新入社員が職場環境にスムーズに馴染みやすくなり、結果的に若手社員の定着率向上や企業全体の活力向上が期待できます。
今日の企業を取り巻く環境では、人材育成が企業の競争力を左右する重要な要素となっています。そうした中で、エルダー制度は単なる教育手段ではなく、企業にとって貴重な人的資産を育成する礎となる要素とみなされています。この制度を通じて、新たな人材がその能力を発揮し、将来の企業を担う存在へと成長することが期待され、制度を適切に活用することで、働きやすい職場づくりと継続的な人材育成の実現が可能となるでしょう。
効果的・効率的に社員の育成を行いたい担当者様は「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」は、部下の育成のための研修にも活用することができます。
自社で作成した教材を簡単に搭載できるため、自社作成の研修教材を用いた社員教育が可能です。
さらに、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただけば、さまざまな対象にあわせた社内教育がすぐに実施できます。
「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートすることができます。
コンテンツには、新入社員向けのものや内定者教育向け、管理職向けなどを含む、100本を超える動画と、理解度を測定することができるビジネス問題が3,000問以上揃っております。
ぜひ「サクテス学びホーダイ」をご活用ください。
SAKU-SAKU Testingは、教育担当者様の声を反映したUIデザインで、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を主催する側・新入社員側、いずれも効率的に利用できます。
ご興味がおありの場合は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。