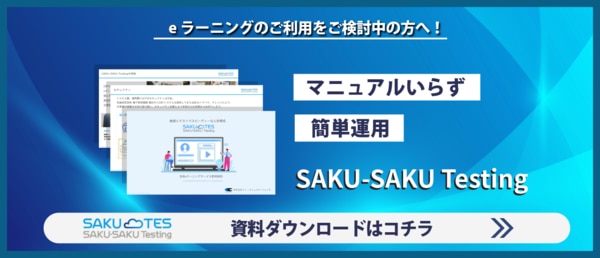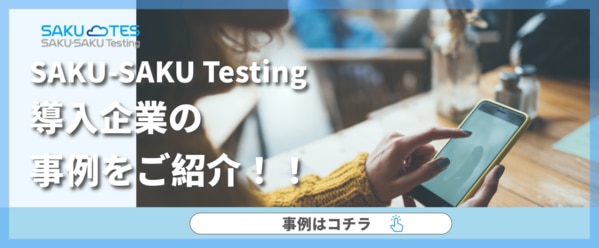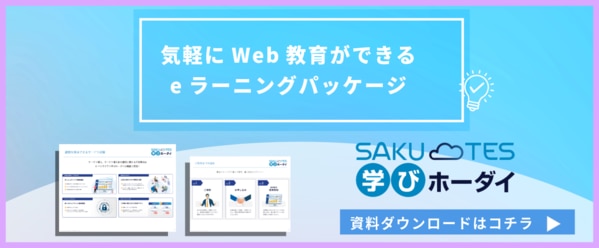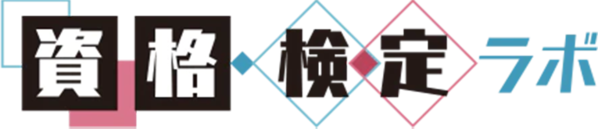新入社員研修はきつい?原因や対策について解説
新入社員研修は、多くの新入社員にとって職場環境になじむために重要ですが、慣れない業務や新たな人間関係に直面し、きついと感じることも少なくありません。本記事では、なぜ研修が「きつい」と感じるのか、その原因を深掘りするとともに、円滑に乗り越えるための具体的な対策をわかりやすく解説します。これからの社会人生活を充実させるため、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.なぜ新入社員研修がきついと感じるのか?
- 1.1.理由①環境の変化によるストレスの増加
- 1.2.理由②集団に馴染めない
- 1.3.理由③最初に覚える情報が膨大
- 1.4.理由④人事担当者や講師の指導についていけない
- 1.5.理由⑤プライベートな時間が削られてしまう
- 2.新入社員研修がきついと感じることで起こり得る問題
- 2.1.メンタルヘルスに影響が出る
- 2.2.離職率の上昇につながる
- 2.3.企業の評判への悪影響
- 3.新入社員研修を「きつい」と感じさせないための工夫
- 3.1.研修の目的や意義を丁寧に説明する
- 3.2.余裕のあるカリキュラムを作る
- 3.3.グループワークやチーム活動を取り入れる
- 3.4.eラーニングを活用して柔軟性をもたせる
- 4.新入社員が「きつい」と感じたときの対処法
- 4.1.研修担当者や上司に相談しやすい環境を整える
- 4.2.適度に休むことでストレスを管理する
- 4.3.メンター制度の利用を検討する
- 4.4.同期との連携を深める
- 5.新入社員研修を「きつい」と感じさせないことで得られるもの
- 5.1.社員の定着率向上による企業への貢献
- 5.2.理解度向上と学びの最大化
- 5.3.ポジティブな研修経験が企業の魅力を向上させる
- 6.新入社員研修のきつさを成功体験に変える工夫
- 6.1.小さな成功体験を積み重ねる
- 6.2.長期的な視点で成長を見据える研修内容を作る
- 7.新入社員研修にぜひeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
なぜ新入社員研修がきついと感じるのか?

まず、新入社員がなぜ研修をきついと感じてしまうのか解説します。
理由①環境の変化によるストレスの増加
社会人となる新入社員は、これまでの生活から大幅に異なる環境に置かれることになります。朝の出社時間や、休憩の取り方などがしっかり管理され、自分の行動が制限されるため、ストレスを感じることが多くなります。
初めての職場での新しいルールや文化にも、戸惑いと緊張感が伴うものです。知らない人とのコミュニケーションや業務にも適応する必要があり、それがさらなる心理的負担を生むこともあります。新入社員がこのような環境の変化にうまく適応できるように支援することが重要です。
理由②集団に馴染めない
新入社員が集団に馴染むことができないと、孤立感を感じることになります。特に、研修の初期段階では、新しい仲間と早い段階で関係を築くことが求められますが、自然な交流がしづらい場面も多いでしょう。
このような状況は、交流が苦手な人にとっては特に負担が大きく、研修がきつく感じられる要因となります。チームビルディングやグループワークを取り入れることで、こうした問題を軽減する対策が必要です。
理由③最初に覚える情報が膨大
新入社員研修では、一度に大量の情報を学ぶ必要があります。会社の業務内容や規則、社内システムについてなど、短期間で様々な内容を吸収しなければならないため、覚えることの多さがきつさを増幅させます。
そのため、学んだ内容をどのように実践に活かせるかを考える余裕がなくなってしまうのです。これによって、自己評価が低くなり、ますます研修がつらいものに感じるでしょう。
理由④人事担当者や講師の指導についていけない
研修プログラムでは、講師や人事担当者からの指導を受けることが主な流れとなります。しかし、個々の受講者がもつバックグラウンドや理解度には差があり、指導内容についていけない新入社員がいるのも事実です。
この結果、周りのペースについていけず、不安や焦りを感じることから「きつい」と思われることに繋がります。そのため、指導法に柔軟性をもたせ、受講者が質問しやすい環境を整えることが重要です。
理由⑤プライベートな時間が削られてしまう
新入社員研修は一般的に、長時間にわたって集中して行われます。自分の時間をもつことが難しく、プライベートな生活が圧迫される感覚が生まれます。この状況は心身の疲労感を引き起こし、研修が厳しいと感じる要因を作ります。
休む時間やリフレッシュの場を設けることで、プライベートも大切にしながら学ぶ姿勢を促すことが求められます。こうした工夫が、新入社員が研修をより快適に受けられるような環境を整える一助となるでしょう。
新入社員研修がきついと感じることで起こり得る問題

新入社員研修がきついと感じることで起こり得る問題もあります。
メンタルヘルスに影響が出る
新入社員研修がストレスの多い環境で行われていると、メンタルヘルスへの影響が考えられます。緊張や不安感が続くことで、精神的な健康が損なわれる可能性があります。特に、はじめての環境や業務に対応しようとする自身へのプレッシャーが強まると、ストレスがより一層増してしまいます。
メンタルヘルスが悪化することで、集中力やモチベーションが低下し、研修そのものへの関心も失われる恐れがあります。こうした状況を改善するためには、サポート体制やコミュニケーションの改善が求められます。
離職率の上昇につながる
新入社員研修が厳しいと感じる場合、離職率の上昇につながることがあります。研修において不安やストレスを抱え続けると、職場に対する印象や期待感が悪化します。
特に、研修が終了した後でも、その時期の経験が影響を及ぼすことが多いです。早期の離職は企業にとっても大きなコストとなりますので、研修の質や内容を見直す必要があるでしょう。
企業の評判への悪影響
新入社員研修が厳しいと感じられると、その影響は企業の評判にも波及します。特に、離職率が高まると、組織全体の雰囲気が悪化し、外部からの評価にも影響が出ることが考えられます。
また、SNSや口コミを通じて不満の声が拡散する可能性もあります。このような状況は、次回の採用活動にもマイナスに働くため、企業イメージを守るためにも効果的な研修方針の見直しが重要です。
新入社員研修を「きつい」と感じさせないための工夫

ここでは、新入社員に研修を「きつい」と感じさせないための工夫について解説します。
研修の目的や意義を丁寧に説明する
研修の目的や意義をしっかりと説明することで、新入社員は自分の位置づけを明確に理解できます。ダイレクトに業務に結びつく内容であることを示すことで、モチベーションが向上する傾向にあります。
また、どのようなスキルや知識を学ぶのかが具体的に示されると、受講者はその実践をイメージしやすくなります。このようにしっかりとした説明がなされることで、研修の内容に対する不安感を軽減し、前向きな姿勢を促進する役割も果たします。
余裕のあるカリキュラムを作る
カリキュラムに余裕があることは、新入社員がストレスを感じないために必要不可欠です。詰め込みすぎると、情報を消化しきれず、疲れてしまうことが多いです。そのため、適度な休憩や振り返りの時間を設けることは、研修効果を最大化するために非常に重要です。
また、進行にゆとりをもたせたスケジュール設計は、柔軟な対応が可能となり、受講者が心の余裕をもつことを助けます。こうした配慮が、新入社員の学びの姿勢に大きな影響を与えるのです。
グループワークやチーム活動を取り入れる
グループワークやチーム活動を取り入れることは、研修の効果を高めるための有効な手段です。新入社員同士の交流を深めることで、孤独感を軽減し、意見交換が活発になります。これにより、研修は一人で頑張る場ではなく、仲間と共に成長する空間となり得ます。
チームでの共同作業を通じて、自己の理解を深めたり、新たな視点を得たりする機会が与えられることで、より充実した学びが生まれます。また、成功体験を共有することができるため、研修のポジティブな印象も強まります。
eラーニングを活用して柔軟性をもたせる
eラーニングの導入は、新入社員研修に柔軟性をもたせるために有効です。オンラインでの学習は、受講者が自分のペースで進めることができるため、忙しい業務の合間でも学びを進められます。特に、自宅での学習が可能になることで、プライベートな時間を確保することもできるようになります。
また、学習内容を自分の必要に応じて選択できるため、興味に基づいた学びが実現します。このように、eラーニングを活用することで、研修の厳しさを軽減し、より充実した内容になることが期待されます。
新入社員が「きつい」と感じたときの対処法

次に新入社員が「きつい」と感じたときの対処法についてみていきましょう。
研修担当者や上司に相談しやすい環境を整える
研修期間中に何か困ったことや不安があれば、研修担当者や上司に相談することが重要です。気軽に話し合える環境が整っていると、受講者自身の不安が軽減され、自身の状況を理解してもらえる可能性が高まります。
相談することで解決策が見つかることもありますし、フィードバックを受けることで、今後の研修においても改善点が明確になりやすくなるでしょう。また、早いうちにサポートを受けることで、心の負担を軽減し、より集中して研修に取り組むことができるようになります。
そのため、企業側は新入社員が相談しやすい環境を整えることが大切です。
適度に休むことでストレスを管理する
研修中は気づかないうちに疲労が蓄積されることが多いです。そのため、適度に休むことがストレス管理には欠かせません。短時間でも小休憩を取り入れたり、ストレッチを行ったりすることで、リフレッシュできる時間が大切です。
研修中は適切な休憩時間を設け、リフレッシュしながら研修を受けてもらえるようなスケジュール設定も大切です。
リフレッシュで得られる少しの余裕が、研修に対するネガティブな感情を和らげてくれるかもしれません。
メンター制度の利用を検討する
メンター制度の導入を考えることも、新入社員が「きつい」と感じたときの対処法として有効です。特に信頼できる先輩や上司がメンターになると、日常的に相談できる相手をもつことができ、気持ちの負担が軽減されます。この制度によって、専門的な知識や経験を相談しやすくなり、心理的なサポートが得られることが大きなメリットです。
メンターとの対話を通して、新入社員は自身の成長に向けた具体的なアドバイスを受けつつ、心理的な安定を図ることができます。また、メンターによるフィードバックは、研修内容を効果的に吸収する手助けにもなります。
同期との連携を深める
新入社員として同じ時間を過ごす同期との連携を深めることも、研修中のストレス軽減に役立ちます。共通の悩みや不安を共有することで、孤独感が和らぎますし、互いに励まし合う関係が築かれることで、チームとしての絆も強化されます。
また、同期と一緒に学ぶことで、情報の共有や助け合いが自然と行われるようになります。こうした連携が、研修進行中のモチベーション向上にも繋がり、仕事に対する前向きな姿勢が生まれるかもしれません。このように、同期とのつながりを大切にすることは、研修を乗り越える大きな力となるでしょう。
新入社員研修を「きつい」と感じさせないことで得られるもの

新入社員研修を「きつい」と感じさせないことによって得られるものがたくさんあります。
ここでは、充実した新入社員研修がもたらす効果について解説します。
社員の定着率向上による企業への貢献
新入社員研修が充実していると、社員の定着率が向上する傾向が見られます。特に、新入社員が安心して仕事に取り組むことができる環境を提供すると、職場の雰囲気が良くなります。定着率が高まることで、人材の流出が減少し、採用や教育にかかるコストを削減することも可能です。
さらに、社員が組織に対して帰属意識をもつことで、業務の効率が上がり結果的に企業の生産性向上につながります。これは、企業としての成長を支える重要な要素となり、その成果がより良いサービスや製品に反映されることが期待されます。
理解度向上と学びの最大化
研修を改善することで、新入社員の理解度も向上します。明確な目的をもったプログラムや柔軟な学習スタイルの導入は、受講者が自身のペースで学ぶ手助けとなります。これにより、知識の定着が促進され、実務に効果的に応用できるようになります。
また、研修内容が受講者に合ったものであると、興味を引きやすくなるため、学びの意欲も高まるでしょう。新入社員が自ら進んで学ぶ姿勢をもつことが、将来的な成長につながることが多いです。このように、理解度を向上させる取り組みは、社員のスキルアップに直結し、企業全体の力を高めます。
ポジティブな研修経験が企業の魅力を向上させる
新入社員研修を充実させることは、企業のイメージ向上にもつながります。研修の質が高いと、新入社員はポジティブな経験をもつことができ、情熱をもって仕事に臨むことが促進されます。これは、企業の文化や価値観を自然に体現する場ともなります。
良い研修は、他の候補者にとってもアピールポイントとなり、優秀な人材を惹きつける要素にもなります。新入社員が感じる満足感や期待感は、企業の評判にも好影響を与えるので、魅力的な職場環境を築くための重要な一環です。企業文化が強化されることで、長期的な競争力も保つことが可能になります。
新入社員研修のきつさを成功体験に変える工夫
ここでは、どのようにしたら新入社員研修のきつさを成功体験に変えることができるかみていきましょう。

小さな成功体験を積み重ねる
新入社員が研修中に小さな成功体験を積むことは非常に重要です。それによって、達成感が得られ、自信を育むことができます。例えば、短時間でのミニプロジェクトやグループディスカッションを設定し、完了後にその成果を評価する仕組みを取り入れると効果的です。これにより、各自の努力が報われる実感が得られ、ポジティブなフィードバックが新たな学びの意欲を刺激します。
また、これらの小さな成功を積み重ねることで、徐々に自己の成長を実感できるようになるのです。感じられる成果が蓄積されると、研修内容に対する興味や関心も高まり、より一層深い学びへの反応が期待できます。
長期的な視点で成長を見据える研修内容を作る
研修内容は短期的な目標だけでなく、長期的な成長を見据えたものを作成するのが理想です。新入社員が未来のキャリアを意識できるような内容にすることで、自ずと研修の意義が深まります。業界のトレンドや技能の変化に対応できるような内容を取り入れると、参加者は自らの成長に繋がると実感できます。
具体的には、段階ごとのスキルアップを意識したプログラムを設計し、各段階での目標を設定することで、参加者はその都度挑戦する気持ちをもつことが期待されます。こうした長期的視点の研修プログラムが、成長を実感させ、結果的に「きつい」と感じることが少なくなる環境を構築する手助けとなります。
新入社員研修にぜひeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
本記事では、新入社員研修を実施する上での特におさえたいポイントや新入社員がつらいと感じた際の対応などをご紹介しました。
イー・コミュニケーションズは新入社員研修に活用できるeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」を活用した様々なコンテンツをご用意しております。
「SAKU-SAKU Testing」では、新入社員研修として利用できるコンテンツ「ビジネスベーシック」をご用意しています。
「ビジネスベーシック」では、入社1年目〜3年目までの社会人としての基本を学べる12コースを全45本の動画でご用意しています。
5~15分の動画と確認問題によって、スキマ時間で効率的に知識を定着させることができます。
管理用画面から受講状況やテスト結果が簡単に確認でき、新入社員の受講も簡単に管理ができます。
また、複数のコンテンツがセットされたコンテンツパッケージ「サクテス学びホーダイ」もございます。
サクテス学びホーダイは100本を超える動画と、理解度を測定することができるビジネス問題が3,000問以上登録されています。
また、内定者教育向けのコンテンツから、入社3年目までのビジネススキルをアップさせるコンテンツと、さらに管理職候補から管理職向けのコンテンツが揃っています。
さらに、企業の3大リスクである「コンプライアンス」「ハラスメント」「情報セキュリティ」のコンテンツも入っているため、全従業員向けの教育にもご利用いただけます。
SAKU-SAKU Testingは、教育担当者様の声を反映したUIデザインで、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を主催する側・受講者側、いずれも効率的に利用できます。
ご興味がおありの場合は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。