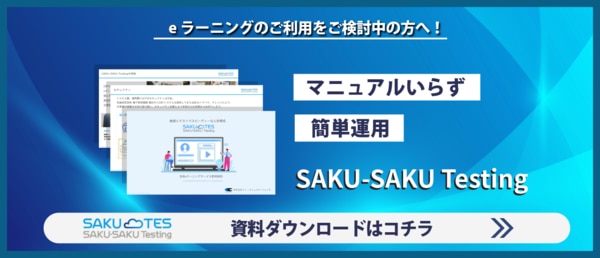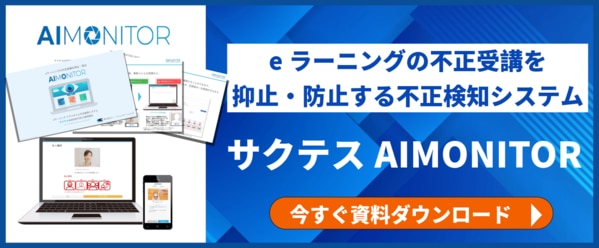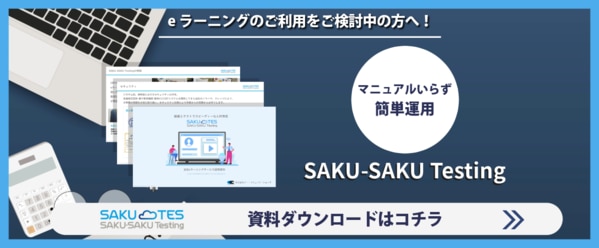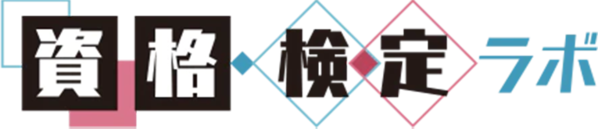社内アンケートの質問例と作り方のポイント
社内アンケートを効果的に実施するためには、まずその目的を明確に設定し、組織が抱える課題や目標にマッチした質問項目を設計することが大切です。効果的なアンケートと実施後の具体的なアクションを的確に行うことで社員満足度の向上や組織の持続的成長につながります。本記事ではアンケートの質問例やポイントなどをご紹介いたします。
目次[非表示]
- 1.社内アンケートとは?
- 2.社内アンケートの目的と重要性
- 3.社内アンケートの質問作成でおさえるべき「二要因理論」とは?
- 4.社内アンケートの種類と選び方
- 4.1.エンゲージメントサーベイ
- 4.2.ストレスチェック
- 4.3.コンプライアンス調査
- 5.社内アンケートの質問項目と例文
- 5.1.業務内容の評価に関する質問
- 5.2.職場環境の改善に関する質問
- 5.3.従業員の満足度に関する質問
- 5.4.会社の制度や福利厚生に関する質問
- 5.5.ワークライフバランスに関する質問
- 5.6.アンケート質問例文まとめ
- 6.社内アンケートを作成する方法
- 6.1.目的を明確にする
- 6.2.質問数を適切に調整する
- 6.3.誘導的な質問を避ける
- 6.4.記名・無記名方式の選択
- 6.5.ツールの活用で効率化
- 7.社内アンケートの注意点と活用方法
- 7.1.アンケート結果の正確な分析
- 7.2.結果をもとにした改善策の実施
- 7.3.従業員のフィードバックを反映する方法
- 8.エンゲージメント研修に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
社内アンケートとは?
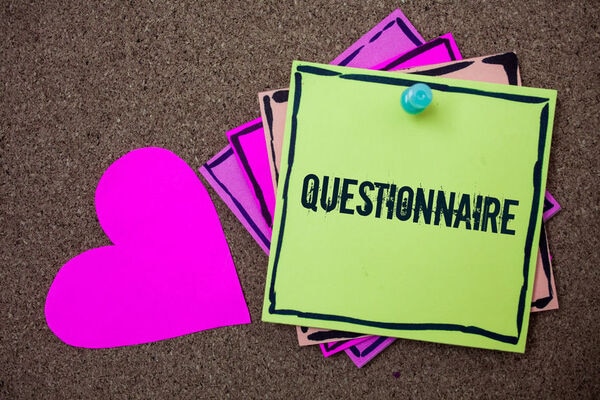
社内アンケートは、従業員を対象に実施される調査手法で、主に従業員の職場環境に対する意見や感想を収集し、組織の改善に役立てることを目的としています。近年では意欲向上や職場環境の改革が多くの企業にとって重要な課題となっており、社内アンケートの活用はその上で欠かせないツールとなっています。
社内アンケートの目的と重要性

社内アンケートを実施する主な目的は、従業員の意見や感想を把握し、それを基に業務や職場環境を改善するための貴重な情報を収集することにあります。企業が従業員満足度の向上を目指す際、この情報は非常に重要な役割を果たします。
また、従業員満足度が向上することで、組織内のコミュニケーションが活発化し、それにより生産性の向上という効果が期待できます。
さらに、企業が定期的にアンケートを実施することは、従業員のニーズや課題を早期に把握するうえで非常に有効です。このプロセスを通じて、適切な対策を迅速に講じることが可能となり、結果として離職率の低下や組織文化の強化といった具体的なプラスの効果が得られます。
加えて、社内アンケートは、経営陣と従業員との間に信頼関係を構築するための重要なツールとしても機能します。従業員が自身の意見が企業によって尊重されていると感じることで、職場への信頼や貢献度が高まり、組織全体がより活性化します。このように、目的が明確かつ効果的に設計された社内アンケートは、企業にとって必要不可欠な取り組みであり、長期的成功につながる鍵となります。
社内アンケートの質問作成でおさえるべき「二要因理論」とは?

社内アンケートの質問作成においては、ハーズバーグの「二要因理論」を活用することで、社員の満足度や不満足度をより効率的に把握することが可能です。この理論は、従業員の職務満足と不満足がそれぞれ異なる要因によって引き起こされると定義し、それを「衛生要因」と「動機付け要因」に分けています。
衛生要因とは?
衛生要因とは、従業員の職務における不満の原因になる要素のことを指します。会社の経営方針や職場環境、給与、就労条件、対人関係、マネジメント方法などが該当します。
これらの要素が適切に管理されていない場合、従業員は不満を抱き、その結果モチベーションの低下や離職率の増加につながる可能性があります。実際、離職の原因の約8割が、この衛生要因によるものとされています。
ただし、衛生要因を改善した場合、従業員が満足感や動機付けを感じるわけではなく、不満が解消される、つまりマイナスがゼロになるイメージです。そのため、従業員の満足度を向上させるには、衛生要因の管理に加えて動機付け要因への配慮も必要です。
動機付け要因とは?
動機付け要因とは、従業員が職務に対して満足感をもつための重要な要素であり、その刺激が従業員のモチベーション向上や積極的な業務遂行につながります。具体的な要因としては、仕事自体のやりがいや達成感、承認、責任、昇進などが挙げられ、これらが従業員の内面的な満足を引き出す基盤となります。これらの要因が満たされることで、従業員は自発的に業務へ取り組む意欲をもちやすくなります。
社内アンケートの種類と選び方

企業が社内アンケートを実施する際には、目的に応じた適切な種類を選ぶことが重要です。社内アンケートの種類にはエンゲージメントサーベイ、ストレスチェック、コンプライアンス調査などがあり、それぞれ異なる目的に基づいて活用されます。
各アンケートには企業が直面する課題や目標に対応するための選択肢が用意されており、導入時にはその目的に最適な選択肢を見極めることが成功のカギとなります。
エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイは、従業員がどれだけ自社に愛着をもち、仕事に対してモチベーションを感じているかを測るための重要な手法です。この調査を通じて、企業は従業員の意見や要望を反映し、組織の改善点を見つけることができます。
具体的な質問内容には、仕事に対する達成感や職場環境への満足度、キャリアの成長意欲、そしてコミュニケーションに関する評価などが含まれます。サーベイの結果を緻密に分析することで、従業員のエンゲージメントを向上させるための具体的な施策を立案する材料が得られます。また、定期的に実施することにより、職場環境や従業員の意識の変化をトレンドとして捉え、長期的な改善へとつなげることが可能です。
実施の際には、特に匿名性を確保することが重要です。従業員がより正直な意見や要望を安心して述べることが可能となり、これにより貴重な洞察を引き出すことができます。その結果、コミュニケーションの円滑化を図り、企業全体の労働環境が改善されると同時に、信頼関係の強化にも寄与します。
ストレスチェック
ストレスチェックは、従業員が抱える精神的な負担を測定し、健康を維持・向上させるための効果的な手法です。この調査を通じて職場環境や業務負荷に対する従業員の不満や課題を把握することができ、早期に必要な対策を講じることに繋がります。
具体的には、業務から生じるプレッシャーや人間関係のトラブル、職場環境が健康に与える影響について細かく質問形式で明らかにしていきます。調査結果を活用することで、従業員のメンタルヘルスを適切に支えるための有効な施策を検討しやすくなり、ストレスの軽減によって業務パフォーマンスの向上も期待できます。
加えて、企業はストレスチェックの結果を分析し、従業員の健康と幸福のために必要なサポートを提供することが求められます。このプロセスは、従業員が感じている不満を解消し、職場の満足度を高める一助となります。また、ストレスチェックを定期的に実施することで、企業が従業員のメンタルヘルスに真摯に向き合っている姿勢を示し、信頼感を高める結果にも繋がるでしょう。
コンプライアンス調査
コンプライアンス調査は、企業の法令遵守や社内規則に対する従業員の認識を把握するための重要な手段です。この調査を通じて、従業員が企業のポリシーや倫理規範、さらにはハラスメント防止に関する取り組みをどの程度理解し、実践しているかを評価することが可能です。
具体的な質問内容には、企業のルールや方針に関する理解度、ハラスメントへの認識、違反行為に対する意識、そして相談窓口の利用状況や報告の実態など、多岐にわたる項目が含まれます。特に、ハラスメントの防止に関する理解や、問題が発生した際に適切な報告が行われているかは、企業文化の健全性を測る重要な指標と言えます。このような調査を通じて、企業が定めたルールが従業員の間で実際に機能しているかを確認することができます。
調査結果をふまえ、対象者の理解を深めるためのトレーニングや研修を強化することで、ハラスメントや違反行為の未然防止に繋げられるでしょう。企業としてコンプライアンス意識を高める努力を継続することは、従業員間の信頼を醸成し、倫理的で持続可能な企業文化の構築に寄与します。さらに、定期的な実施は、長期的な信頼関係の構築や企業全体の健全な運営にも大きく貢献するでしょう。
コンプライアンス研修にイー・コミュニケーションズのコンプライアンスコンテンツをご活用ください。
動画と確認テストで学ぶ「弁護士が解説 よくわかる企業のコンプライアンス講座」やテスト問題でコンプライアンスを学ぶ「コンプライアンス総合問題集」など、企業のコンプライアンス研修に活用できるeラーニングコンテンツをご用意しています。
社内アンケートの質問項目と例文

社内アンケートの効果を最大限に引き出すためには、的確な質問項目の設定が極めて重要です。質問項目は、従業員の意見や感情を正確に把握し、企業としての課題や改善点を整理するための基盤となります。具体的で多角的な観点から質問を設置することで、より有益で信頼性の高い情報を得ることが可能です。以下では、代表的な質問例文も交えながら、それぞれの視点について詳しく解説します。
業務内容の評価に関する質問
業務内容の評価に関する質問は、従業員の職務に対する意義や達成感を測るうえで非常に重要です。こうした評価を適切に行うためには、仕事のやりがいや面白さを含む、業務そのものに関連した設問を設けることが効果的です。たとえば、「現在の業務内容に達成感を感じていますか?」や「自分が担当している業務の難易度に満足していますか?」といった具体的な質問を通じて、従業員が抱える満足感や問題点を明らかにすることができます。
これらの設問を活用することで、従業員の実際の業務に対する関心や興味の度合いを評価することが可能です。この評価結果は、業務内容を見直し、改良する上で価値のある情報となります。また、評価を基にした業務の改善により、従業員の満足度が向上するだけでなく、業務効率の向上にも繋がると考えられます。業務内容の評価を通じて、職場全体のパフォーマンス強化を実現することも可能です。
職場環境の改善に関する質問
職場環境に関する質問は、従業員が快適に働けるかどうかを確認するために重要な役割を果たします。具体的には、「職場の清潔感や設備状況に満足していますか?」や「騒音レベルに関して不満を感じていますか?」といった設問を通じて、物理的な環境に対する評価を収集できます。
こうした質問を通じて、従業員が日常業務で抱えるストレス要因を特定しやすくなります。そこで、従業員の声を集める工夫をすることが大切です。たとえば、定期的なアンケートや個別面談を取り入れることで、幅広い意見を収集し、細かな改善点を洗い出す機会を増やせます。さらに、職場環境の改善策が必要である場合、従業員の意見を反映しながら実施するべき優先順位を明確にする手助けにもつながります。
また、収集した情報を基に具体的な改善を行うことは、単に物理的な環境を良くするだけでなく、従業員の満足度やモチベーションを高める重要な要素となります。これにより業務の効率が向上し、より良い環境を生み出すための継続的な努力を促す仕組みが形成されるでしょう。職場環境を向上させるためには、適宜工夫を凝らし、柔軟かつ積極的に取り組む姿勢が求められるのです。
従業員の満足度に関する質問
従業員の満足度に関する質問は、従業員が職場に対してどのような感情を抱いているかを知るために不可欠です。「職場の雰囲気について満足していますか?」や「上司とのコミュニケーションに満足していますか?」といった具体的な質問を設けることで、満足度だけでなく、不満の原因を含む、仕事環境や人間関係における課題を明らかにすることができます。
従業員の満足度が高い場合、仕事へのモチベーションが向上し、結果として企業全体の生産性や業績が向上する可能性が高まります。一方で、不満を抱えている従業員が多い場合、離職率が上昇したり、チーム全体のパフォーマンスが低下するリスクがあるため、早期の改善が求められます。
これらの質問を通じて得られたフィードバックを分析することで、満足度の向上に向けた的確な戦略を立てることが可能です。不満が特定された場合には、迅速に対応し、改善策を講じることで、従業員が安心して働ける職場環境を築くことができます。このような取り組みは、組織のエンゲージメント向上だけでなく、企業全体の成長にも寄与するでしょう。
会社の制度や福利厚生に関する質問
会社の制度や福利厚生に関する質問は、従業員の生活の質を向上させるために重要です。従業員一人ひとりのニーズに応じた福利厚生の見直しや改善を行うために、「提供されている福利厚生は、自分のライフスタイルや働き方に適していますか?」または「制度について理解しやすい説明やサポートが提供されていますか?」といった具体的な質問を投げかけることは効果的です。こうした質問を通じて、従業員が抱える課題や改善点を明確化し、それに基づいた適切なサポートを提供することが企業に求められます。
さらに、会社が福利厚生制度を時代の変化や従業員の多様なライフステージに合わせて柔軟に対応していくことは、働きがいや社員満足度の向上に直結します。また、具体的な提案が従業員から寄せられた場合には、それを反映する努力を行うことで、福利厚生に対する信頼感が高まるとともに、会社全体の職場環境の向上が期待できます。このように従業員の声を積極的に取り入れる姿勢は、会社運営の質を向上させる重要な要素となります。
ワークライフバランスに関する質問
ワークライフバランスに関する質問は、従業員が仕事とプライベートをどのように両立させているかを確認し、その実態を把握するために非常に有効です。「仕事と私生活の両立に満足していますか?」や「残業時間についてどう感じていますか?」といった具体的な質問を設けることで、従業員の生活の質や健康状態を把握することが可能となります。特に、テレワークの普及に伴い、仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすいため、それが従業員の心身の健康にどのような影響を与えているかを把握することが重要です。
多くの従業員は、ワークライフバランスが取れていると、家庭生活や自己成長にポジティブな影響をもたらすと感じています。このような質問で得られたデータをもとに、企業は働く環境のさらなる見直しや改善を行うことで、従業員の健康維持や仕事の満足度向上をサポートできます。特にテレワーク環境に適した柔軟な勤務制度や、従業員の健康を考慮した施策を取り入れることが、従業員一人ひとりの豊かなライフスタイルを実現する鍵となります。結果として、このような取り組みが組織全体の活力を向上させ、企業の成長にもつながるといえるでしょう。
アンケート質問例文まとめ
これまでに解説したアンケート質問例文を表でまとめます。
|
業務内容の評価に関する質問 |
現在の業務内容に達成感を感じていますか? |
自分が担当している業務の難易度に満足していますか? | |
業務が自分の適正にあっていると実感しますか? | |
|
職場環境の改善に 関する質問 |
職場の清潔感や設備状況に満足していますか? |
騒音レベルに関して不満を感じていますか? | |
自分の意見を率直に言える雰囲気だと感じていますか? | |
|
従業員の満足度に 関する質問 |
職場の雰囲気について満足していますか? |
上司とのコミュニケーションに満足していますか? | |
上司とのコミュニケーションに満足していますか? | |
|
会社の制度や福利厚生に 関する質問 |
提供されている福利厚生は、自分のライフスタイルや働き方に適していますか? |
制度について理解しやすい説明やサポートが提供されていますか? | |
休暇の取得促進や労働環境の改善が図られていると思いますか? | |
|
ワークライフバランスに 関する質問 |
仕事と私生活の両立に満足していますか? |
残業時間についてどう感じていますか? | |
休日に業務のことで心配することはありませんか? |
社内アンケートを作成する方法

社内アンケートの作成は、従業員の意見を集め、企業の改善に繋げるための重要な方法です。その方法について見ていきましょう。
目的を明確にする
社内アンケートを成功させるためには、まずその目的を明確に設定することが不可欠です。企業がアンケートを実施する際、具体的な目的をもつことで質問内容が緻密になり、得られるデータがより実践的で有意義なものになります。たとえば、従業員のエンゲージメント向上を目指す企業であれば、モチベーションや仕事のやりがいといった要素に関連する質問を組み込むことが重要です。
さらに、業務改善を目標とする場合には、具体的な業務課題や職場環境の課題に焦点を当てた質問を設けることで、実態に即したデータを取得できます。もし目的が不明瞭であると、収集したデータの分析やその後の解釈が困難となり、企業にとって効果的な施策の策定が難しくなります。したがって、アンケートを実施する際には、最初に明確な目的を設定し、企業全体の目標に基づいた適切な設問を用意することが成功の鍵を握ると言えるでしょう。
質問数を適切に調整する
社内アンケートを実施する際、質問数の調整は極めて重要です。多すぎる質問は従業員にとって負担となり、途中で回答を諦める原因につながります。そのため、最適な質問数の設定が必要です。一般的には10問程度の質問が理想とされていますが、アンケートの目的や内容に応じて柔軟に調整しましょう。たとえば、特定のテーマに焦点を当てたアンケートでは、必要に応じて関連性の高い質問例や具体的な項目を加えることで、深堀りした意見を集めることができます。
一方、全体的な満足度を把握するアンケートの場合は、必要最低限の質問数に留めることが効果的です。各質問は明確かつ具体的な表現で構成し、回答者が簡単に理解し回答できる内容にすることが肝要です。その際、アンケートの目的に合致する適切な項目を慎重に選び抜くことで、回答の質を向上させることができます。こうした配慮により、回答率が高く、効果的なアンケート運営が実現可能となります。
誘導的な質問を避ける
社内アンケートを実施する際、誘導的な質問を避けることが極めて重要です。誘導的な質問は、回答者に特定の意見を促したり、自社に都合の良い回答を引き出す恐れがあり、結果として正確性が損なわれる可能性があります。たとえば、アンケート中に「この新しい制度は素晴らしいと思いますか?」というような質問を使用すると、ポジティブな回答を引き出しやすくなります。これに対し、「この新しい制度についてどう感じますか?」というような中立的で反応を制限しない形式の例文が効果的です。このアプローチを取ることで、従業員の率直な意見を収集しやすくなります。
このように、中立性を保った質問を用いることで、企業は従業員の率直な意見や感想を引き出し、具体的な改善措置を講じるための貴重な情報を得ることができます。結果として、信頼性の高いデータに基づく意思決定が可能となり、社内のエンゲージメント向上にも大きく寄与します。
記名・無記名方式の選択
社内アンケートの成功には、記名方式と無記名方式の適切な選択が重要です。記名方式を採用すると、個々の回答に対して具体的なフィードバックを行いやすく、従業員の意見や要望をより正確に把握できます。しかし、回答者が特定されることで、率直な意見を表明することに躊躇する場合もあるため、特にデリケートな問題を取り扱う際には慎重な判断が必要です。
無記名方式は、回答者が自由に意見や要望を表現しやすい特性をもっており、素直で正直なフィードバックを引き出すのに最適です。この方式を用いることで、組織内の隠れた課題を明らかにし、問題点の改善へ向けた具体的な手がかりを得ることが期待できます。また、無記名形式は従業員の心理的安全性を高める効果もあり、より多くの視点を収集することに役立ちます。
アンケートの目的に応じて、記名方式と無記名方式のどちらがより効果的であるかを慎重に検討することが大切です。また、場合によっては両方の方式を併用し、それぞれの強みを活かすことも効果的な手法となります。
ツールの活用で効率化
社内アンケートの作成や実施において、ツールの活用は業務効率を大幅に向上させる重要な手段となります。特に、オンラインアンケートプラットフォームを活用すれば、設問の作成から配布、さらに回答の集計に至るまでのプロセスがスムーズに進行できます。これにより、従業員からの回答をリアルタイムで収集でき、迅速かつ正確な分析が可能となる点が大きな利点です。
さらに、これらのツールには無料または低コストで利用できるものが多く、加えて、直感的な操作が可能な設計がされているため、ITスキルに自信がない担当者でも安心して活用できます。特にテンプレート機能を活用することで、アンケート設計の時間を効率的に削減できるだけでなく、調査目的に合った内容へのカスタマイズも容易になります。このように、目的に応じたツールを有効活用することで、業務プロセスの効率がさらに高まり、より精度の高い有益なデータの収集が可能となります。
社内アンケートの注意点と活用方法

社内アンケートを実施する際には、注意点をしっかりと押さえることが重要です。実施後の遂行すべき事項を確認しましょう。
アンケート結果の正確な分析
社内アンケートの結果を正確に分析することは、組織の改善策を導き出すために不可欠です。まず、集計したデータを単体で見るのではなく、施策の目的に応じた切り口で分析することが重要です。具体的には、部署や職種ごとの傾向を把握するためにクロス集計を活用します。また、年齢や役職といった属性別にデータを分析することで、従業員の多様なバックグラウンドに基づいた深い洞察が得られます。これにより、特定のグループが抱える問題点を明確にし、効果的な対応策を打ち出すことが可能となります。
さらに、定量的なデータだけでなく、自由回答の内容も丁寧に確認する必要があります。従業員の具体的な声を理解することで、数値では表現できないニュアンスや課題を把握することができます。その際、分析結果は簡潔かつ分かりやすい形で報告することが求められます。適切な分析手法を用いることで、結果に基づく実行可能な改善策を形成し、組織のエンゲージメント向上に寄与できるのです。さらに、データに基づいた意思決定は、長期的に見ても企業の競争力を高める重要な要素となります。
結果をもとにした改善策の実施
社内アンケートの結果を的確に分析し、改善策を実施することは、従業員の満足度向上や組織の効率化につながります。まず、収集したデータをもとに具体的な課題を特定し、従業員の意見やニーズを反映した施策を立てる際には、その内容を従業員にわかりやすく伝えるための工夫が重要です。このような工夫を取り入れることで、従業員が改善策の意図を正しく理解し、実施に協力的な姿勢を示しやすくなります。また、改善策の内容や進捗を透明に共有することで、従業員の信頼を得やすくなるため、施策全体の効果が高まるでしょう。
さらに、施策が効果を発揮しているかどうかを定期的に評価し、その状況に応じて見直すことも必要です。中長期的に結果を検証し、新しい課題が見つかった場合には柔軟に対応する姿勢が、継続的な改善を実現します。この一連の取り組みを通じて、職場内のコミュニケーションが深化し、職場環境の質も大きく向上するでしょう。その結果、従業員のエンゲージメントが高まり、業績の向上にも良い効果をもたらします。
従業員のフィードバックを反映する方法
従業員のフィードバックを効果的に反映させるためには、まず、回答の内容を丁寧に分析することが不可欠です。集めた意見を具体的なテーマやトピックに分け、どのような傾向や課題が浮かび上がっているかを把握し従業員の要望を正確に理解することが重要です。その後、従業員に対してフィードバックの結果を報告し、どの意見がどのように反映されるかを具体的に説明することで、従業員とのコミュニケーションを活性化させることができます。このようなプロセスは、従業員が自分の意見が価値のあるものとみなされていると感じる要因となり、更なる参加意欲の向上に繋がります。
さらに、具体的な改善策を積極的に実施し、その結果を定期的に報告することが欠かせません。フィードバックの状況を継続的に確認し、必要に応じて施策を見直す柔軟な姿勢を保つことで、従業員の要望をより適切に反映させることが可能です。また、オープンなコミュニケーションを通して従業員との信頼関係を深めることで、組織全体のエンゲージメントが向上します。これらすべての取り組みを通じて、従業員が働きやすい環境を築き、組織の成長を促進することが実現できるでしょう。
エンゲージメント研修に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
社員の満足度向上を目指す、エンゲージメント研修には、離職率の低下や生産性の向上など、多くのメリットがあります。
自社でエンゲージメント研修を実施する際は、イー・コミュニケーションズの「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。SAKU-SAKU Testingは豊富な学習機能を備えたeラーニングプラットフォームです。
自社で作成したスライドや動画を組み込んだオリジナルの学習プログラムを作成することができます。そのほか、多彩なコンテンツを利用できますので、エンゲージメント研修以外の社員教育にもお役立ていただけます。
ご興味のある方はぜひ一度お問い合わせください。