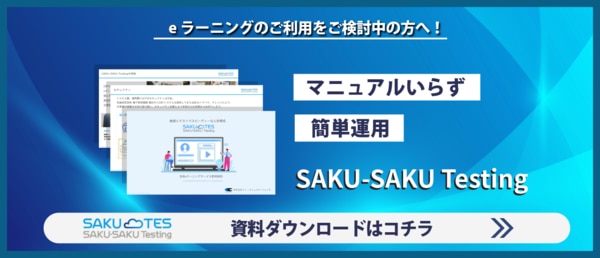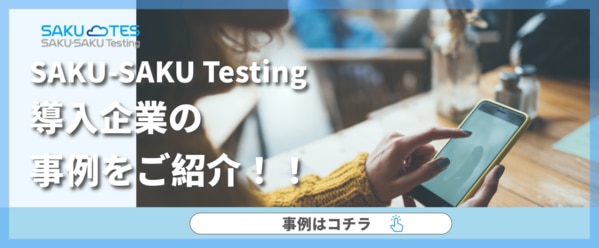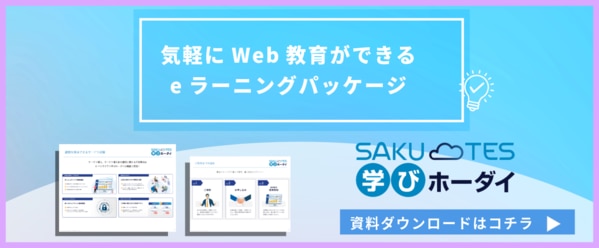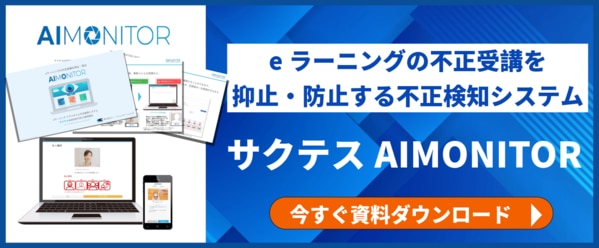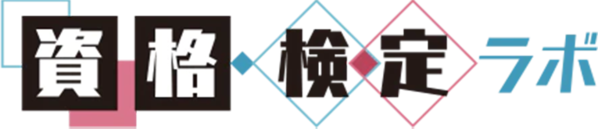センスメイキングとは?重要視されている理由と職場での活用方法を解説
センスメイキングは、現代のビジネスシーンにおいてますます重要性が増しているスキルの一つです。膨大な情報と複雑な状況に直面する日々の中で、意味を見出す力は、個人だけでなくチームや組織全体の成果を大きく左右します。
日々の業務やプロジェクトの推進において、センスメイキングを活用することで、より的確な意思決定が可能となり、目標達成への道筋が明確になります。
本記事では、このセンスメイキングがいま組織においてなぜ重要視されているのか、その理論的背景や具体的な活用法、さらに人事・教育担当者としてどのように現場に導入できるかについて詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.センスメイキングとは何か
- 2.センスメイキングが注目される背景
- 3.センスメイキングの理論的基盤と要素
- 3.1.センスメイキングの主な特徴(ワイクのモデルを踏まえて)
- 3.1.1.1.アイデンティティの再構築
- 3.1.2.2.レトロスペクティブ(振り返り)
- 3.1.3.3.社会的プロセス
- 3.1.4.4.手を動かすことで進む(エンアクトメント)
- 3.1.5.5.常に継続的
- 3.2.情報の選択とストーリー化
- 4.センスメイキングが組織にもたらすメリット
- 4.1. 意思決定の質とスピードの向上
- 4.2.イノベーションや創造性の喚起
- 4.3.エンゲージメントや組織文化の醸成
- 4.4.組織変革への対応力強化
- 5.現場での活用ヒント:人事・教育担当者ができること
- 5.1.1. 研修やミーティングで「自分ごと化」のワークを取り入れる
- 5.2.2. 「意味づけ」を深めるフィードバックや面談
- 5.3.3. 組織としてのストーリーテリングを大切にする
- 5.4.4. ワークショップやアクションラーニングの場を設ける
- 5.5.5. OJTで先輩・上司が質問を活用する
- 6.センスメイキング促進に役立つツール・実践事例
- 6.1.活用できるツールやフレームワーク
- 6.1.1.K-W-Lチャート
- 6.1.2.デザイン思考プロセス
- 6.1.3.ジャーナリングツール・ナレッジシェアのプラットフォーム
- 6.2.実践事例の一例
- 7.センスメイキングの定着を妨げる要因と対策
- 7.1.妨げる要因
- 7.1.1.トップダウン型文化が強い組織
- 7.1.2.評価や会議が形式的になっている
- 7.1.3.急激な変化に対する不安や抵抗感
- 7.2.対策
- 7.2.1.リーダーの意識啓発
- 7.2.2.制度や評価基準の見直し
- 7.2.3.少人数から始めるワークショップ
- 8.まとめ
- 9.社員教育に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
センスメイキングとは何か

私たちが日々働く中で、新たな情報や出来事に直面したとき、どのように「意味づけ」をしているでしょうか。
たとえば、組織で新しいプロジェクトが始まったり、業界の動向が急に変化したりする場面では、多くの情報が流れ込みます。そのとき、「なぜこれが重要なのか」「自分や組織にとってどのような意味があるのか」を素早く理解し、行動に落とし込む力が求められます。
こうした「自分なりにストーリーを組み立てて解釈し、次のアクションにつなげるプロセス」を、組織行動論では「センスメイキング(Sensemaking)」と呼びます。もともとは組織や個人が未知の現象に直面したとき、後付けで「意味づけ」していく様子を解明するために注目されてきた概念ですが、近年はビジネスの現場でも大きな注目を集めています。
センスメイキングが注目される背景
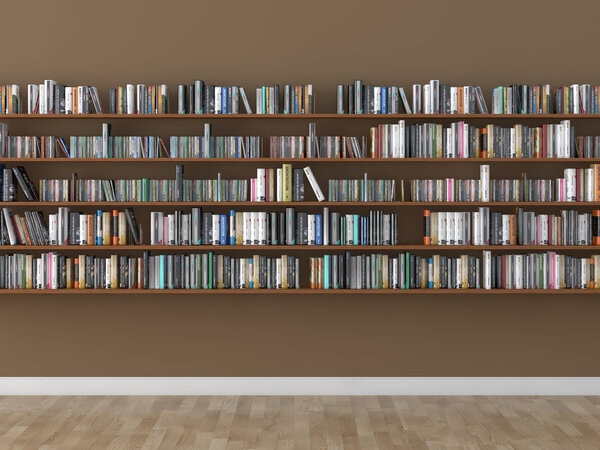
現代のビジネス環境は、VUCAと呼ばれる「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧さ)」が高まる時代だといわれます。テクノロジーの急激な進歩やリモートワークの普及、そしてグローバル化によって、企業を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、組織が対処すべき情報量やスピードは増す一方です。
これまでのように「上司や経営陣からの指示を待つ」「答えが決まった作業を正確にこなす」だけでは、変化に対応しきれなくなっています。組織全体でスピーディに意思決定を行い、メンバー一人ひとりが主体的に課題に取り組むためには、自ら考え、情報に意味を与え、行動するプロセスが不可欠です。
センスメイキングは、まさにこの「変化の中から自分なりの解釈を導き、行動の軸を作る」能力を高める概念として、多くの企業や研究者から注目されています。多様化が進む組織では、個々のバックグラウンドが異なるため、共通理解をもつのは簡単ではありません。そこで、メンバーそれぞれが自分の視点を言語化し、相互に共有し合うことで、チームや組織としての共通認識を作り上げていく必要があります。センスメイキングは、そのための基礎スキルと言えるのです。
センスメイキングの理論的基盤と要素

センスメイキングを語る上で欠かせないのが、組織論の研究者であるカール・ワイク(Karl E. Weick)の業績です。ワイクは、組織や集団が未知の出来事や混乱した状況に直面したとき、どのように「意味づけ」を行って次の行動に移すのかを解明するため、多くの事例研究や理論モデルを提示してきました。
ここでは、ワイクが提示するセンスメイキングの特徴について解説します。
センスメイキングの主な特徴(ワイクのモデルを踏まえて)
1.アイデンティティの再構築
人は出来事を解釈する際に、「自分はどういう存在か」というアイデンティティを再確認・再定義しながら、意味づけを進めます。新しい業務に取り組むときや部署異動を経験するときは、過去の経験や自己認識を手がかりに「これは自分にとってどういう意義があるか」を考えるのです。
2.レトロスペクティブ(振り返り)
センスメイキングは「起きたことを後付けで振り返って意味づけする」性質があります。まずは行動や出来事が起きて、その後で「なぜこれが重要だったのか」「どのような意味があるのか」を整理し、理解を深めます。多忙なビジネス環境であっても、定期的に振り返りを行うことで自分なりの学びを獲得できます。
3.社会的プロセス
センスメイキングは、個人の頭の中で完結するものではありません。周囲のメンバーと対話したり、共通の言葉やストーリーを作り上げていく過程で育まれます。そのため、チームや組織のコミュニケーションの質がセンスメイキングの成否を左右します。
4.手を動かすことで進む(エンアクトメント)
「意味づけ」が先にあって行動するのではなく、むしろ行動しながら意味づけが形成されるのがセンスメイキングの特徴です。試行錯誤をしながら、実際の行動と振り返りを繰り返すことで、徐々に解釈の枠組みが構築されます。
5.常に継続的
組織は常に新しい事象や情報にさらされており、センスメイキングは1回で完了するものではありません。むしろ、日々のコミュニケーションや学習の中で絶えず更新されていく「動的なプロセス」といえます。
情報の選択とストーリー化
多くの情報の中から何を選び取り、どのようにストーリーとして組み立てるかは、個々人の経験や所属する組織文化によって異なります。たとえば、同じ業績報告会の結果を聞いても、「これはチャンスだ」と捉える人もいれば「リスクが大きい」と捉える人もいるでしょう。センスメイキングでは、その多様性自体を肯定し、むしろ活用して「組織としての共通の理解」へとつなげていきます。
こうした理論的背景を踏まえると、センスメイキングとは単なる「頭の中の思考プロセス」ではなく、組織やチーム全体のコミュニケーションや文化にも深く関わる概念であると理解できます。
センスメイキングが組織にもたらすメリット

センスメイキングの活用は組織にさまざまなメリットをもたらします。ここでは、センスメイキングによるメリットを解説します。
意思決定の質とスピードの向上
センスメイキングが活発に行われている組織では、メンバーが自ら考えて状況を把握し、行動に移すまでのスピードが速くなります。たとえば、新しい市場への参入や突発的なクレーム対応など、想定外の事態に直面しても、チーム全体が共通の問題意識をもちやすくなり、素早い意思決定が可能になります。
イノベーションや創造性の喚起
「これはこういう意味があるかもしれない」「この情報はこう繋がるのではないか」という解釈が活発になることで、固定概念や慣習にとらわれにくくなります。多角的な視点で物事を捉えられるようになるため、新しいアイデアや製品・サービスの開発につながりやすいのです。
エンゲージメントや組織文化の醸成
センスメイキングを重視する職場では、個々人の経験や意見を積極的に共有する場が自然と増えます。それにより、自分の考えが認められる安心感や、チームとしての一体感が高まり、従業員のエンゲージメントが向上します。また、情報を透明化し、解釈を共有する文化が根づけば、ミスコミュニケーションや誤解による摩擦が減り、健全な組織風土が育まれます。
組織変革への対応力強化
組織再編やデジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進など、大きな変革期においても、センスメイキングが進んでいる組織は変化をポジティブに受け止め、次に打つ手を考えやすい土壌があります。全社員が変化の意味を理解し、自分ごととして捉えられるようになるため、抵抗勢力を最小限に留めながら変革を進められるのです。
現場での活用ヒント:人事・教育担当者ができること

ここからは、人事・教育担当者がどのようにセンスメイキングを促し、組織全体に広げていくかについて、具体的なヒントをいくつか紹介します。
1. 研修やミーティングで「自分ごと化」のワークを取り入れる
集合研修やオンライン研修などで新しいスキルや知識を学ぶ際、ただ一方的に講義を行うだけではセンスメイキングは進みません。受講者が自分の業務や経験を振り返りながら、「これは自分にどう役立つのか」「職場でこの知識を活かすとどうなるか」を考え、言葉にするステップを用意しましょう。
ケーススタディ:架空のビジネスケースを題材にチームでディスカッションし、「この状況で自分たちが取るべき行動は何か」を考えさせる。
振り返りシート:毎回の研修や会議の終了時に「今日学んだこと」「自分の業務にどう活かせるか」を書き出すシートを配布し、提出させる。
2. 「意味づけ」を深めるフィードバックや面談
評価面談や1on1ミーティングでは、単に目標達成度合いや課題を確認するだけでなく、以下のような問いを投げかけてみてください。
「この経験からどんな学びを得ましたか?」
「それはあなたのキャリアにどう結びついていますか?」
「今後、どういう行動をとればより良い結果が得られそうですか?」
本人が過去の行動を振り返って「自分にとってどういう意味があったか」を言語化できると、センスメイキングが加速します。
3. 組織としてのストーリーテリングを大切にする
経営層やリーダーがビジョンや方針を示す際、「なぜこれを大事にしているのか」「そこに至るまでのストーリーは何か」を具体的に共有することが重要です。ただの数字目標やスローガンだけでは、人はなかなか腹落ちしません。背景や失敗談、紆余曲折を含めた物語を語ることで、メンバーが自分なりの解釈をしやすくなり、行動のモチベーションが高まります。
4. ワークショップやアクションラーニングの場を設ける
仕事上の課題をチームで持ち寄って一緒に解決策を探すアクションラーニングの手法は、センスメイキングと相性が良いです。実際の課題を題材に「何が問題か」「なぜ重要か」を参加者同士で解釈し合い、行動計画を立てて実行・振り返りを繰り返します。このとき、担当者は「なぜそう考えたのか?」という問いを頻繁に投げ、参加者同士が思考プロセスを共有できるようファシリテートすると良いでしょう。
5. OJTで先輩・上司が質問を活用する
OJTの場面では、上司や先輩が「こうしろ」と指示するだけでなく、後輩や新入社員の「解釈プロセス」を引き出す質問が大切です。
「この業務をやってみて、どんな意外な発見があった?」
「もっと良い方法はないと思う?」
「次に同じような仕事をするとき、どう変えてみたい?」
こうした質問に答えることで後輩は、自らの行動を意味づけし、次のステップに活かす気づきを得ます。
センスメイキング促進に役立つツール・実践事例

センスメイキングの推進には、さまざまツールの活用が有効です。ここでは、役立つルーツや実践事例について解説します。
活用できるツールやフレームワーク
K-W-Lチャート
K(Know):既に知っていること
W(Want to Know):知りたいこと
L(Learned):学んだこと
研修や学習の前後にこの3つを整理することで、参加者が自分の頭の中で情報を整理し、学習内容の「意味づけ」を強化できます。
デザイン思考プロセス
観察やインタビューから始まり、問題の定義・アイデア創出・プロトタイピング・テストへと進む一連の流れは、試行錯誤しながら意味を作るプロセスそのものです。新規事業やサービス開発だけでなく、社内の課題解決にも応用できます。
ジャーナリングツール・ナレッジシェアのプラットフォーム
社内SNSやLMS(Learning Management System)で、プロジェクトごとの成功事例や失敗事例を共有するときに「何が起き、何を学んだか」のストーリーを蓄積していく仕組みをつくると、組織全体でセンスメイキングの風土が育ちます。
実践事例の一例
ある製造業の企業では、DXを推進するにあたり、各部署から選抜した若手社員で「アジャイルチーム」を結成しました。プロジェクトの節目ごとに全員で振り返り会を行い、「今回の試作で顧客からどういう反応があったか」「そこから見える次のアクションは何か」を全員でディスカッション。こうしたプロセスを重ねることで、自分たちの成果に対する認識が深まり、新しい技術導入への不安も和らいだそうです。
結果的に、組織全体でDXに前向きな姿勢が育ち、経営陣からも評価されるプロジェクトになりました。
センスメイキングの定着を妨げる要因と対策

センスメイキングを推進させようとしても、なかなか定着しないといった事態も起こり得ます。ここでは定着を妨げる要因とその対策について解説します。
妨げる要因
トップダウン型文化が強い組織
常に指示が降りてくるだけの環境では、個人が「意味づけ」する前に答えを与えられてしまい、センスメイキングを行う余地が生まれにくい。
評価や会議が形式的になっている
「とりあえずKPIを達成したかどうかだけを確認する」面談や定例会議では、意味づけを深める対話が不足してしまう。
急激な変化に対する不安や抵抗感
新しい取り組みや制度を導入するとき、必要性が理解されないまま進められると、ネガティブな解釈が先行してしまいがち。
対策
リーダーの意識啓発
まずは管理職やプロジェクトリーダー層が、センスメイキングの意義を理解し、自ら実践する姿勢を示す必要があります。
制度や評価基準の見直し
意味づけや学びの共有を奨励するような制度を設け、例えば「プロセス重視の評価項目」や「振り返りを重んじるカルチャーづくり」を推進します。
少人数から始めるワークショップ
組織全体で一気に変えるのが難しい場合、まずは意欲のある部署やプロジェクトチームで試験的に取り入れ、成果を発信していくと抵抗が和らぎます。
まとめ

センスメイキングは「自分や組織にとって、ある出来事や情報はどんな意味を持つのか」を後付けで解釈し、共有するプロセスです。変化が激しい現代においては、従業員が主体的に情報を捉え、素早く行動につなげるための重要なカギとなります。人事・教育担当者としては、研修や面談、OJT、制度設計など、さまざまな場面でセンスメイキングを後押しする仕組みづくりが可能です。
今後、テクノロジーがさらに進化し、AIや自動化が進む中でも、「人間が意味を作り出す力」はより一層求められるでしょう。単純作業は機械が代替しやすくなりますが、複雑な文脈を理解し、新しい視点を生み出す力は人間特有の能力です。組織としても個人としても、この力を強化していくことで、これまでにないイノベーションや持続的な成長が期待できます。
社員教育に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
社員教育にイー・コミュニケーションズのeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」がおすすめです。
「SAKU-SAKU Testing」は自社で作成した教材を搭載して利用できるので、教育プラットフォームとして活用することが可能です。
また、自社コンテンツを搭載するeラーニングプラットフォームとしての利用以外に、あらかじめ社員教育に必要な教材がパッケージ化されている「サクテス学びホーダイ」など、さまざまなニーズに対応したeラーニングのご提案が可能です。
ご興味がおありの場合はお気軽にお問い合わせください。