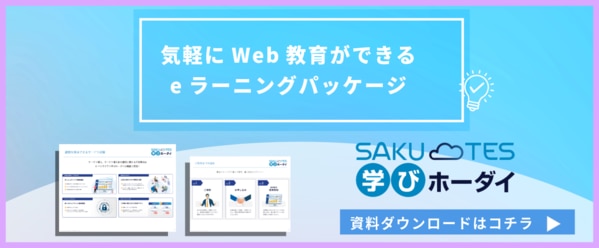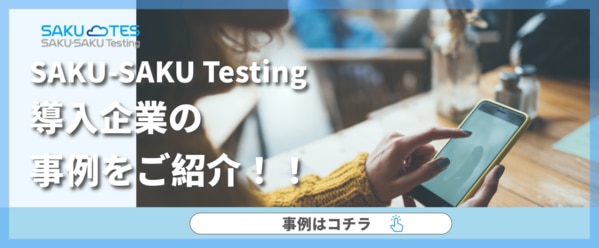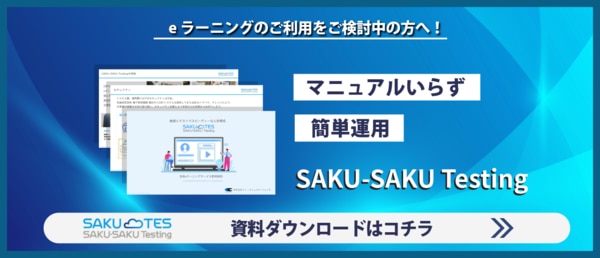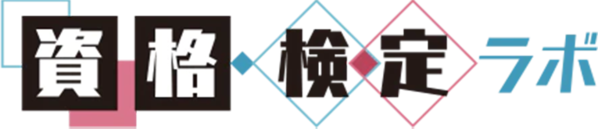OJT研修のポイントやメリットについて解説
OJT研修は、職場での実務を通じて実践的なスキルや知識を習得する育成手法として、多くの企業で活用されています。この育成手法は、新入社員や若手社員が業務を通じて学び、即戦力として成長するのに最適です。業務現場での経験や、指導者との密なコミュニケーションを通じて実践的な対応力を身につけるためには、計画性や指導者の育成が重要なポイントとなります。
本記事では、OJT研修を行う際のポイントやメリットについて解説しますのでお役立ていただけますと幸いです。
目次[非表示]
- 1.OJT研修とはなにか
- 2.OJTとOFF-JTの違いとは?
- 3.OJTの目的と特徴
- 4.OJT研修の具体的な実施方法
- 4.1.OJTの4段階ステップ
- 4.1.1.ステップ①「見せる」
- 4.1.2.ステップ②「説明する」
- 4.1.3.ステップ③「やってもらう」
- 4.1.4.ステップ③「評価する」
- 4.2.OJTの計画とスケジュール作成
- 4.3.指導者の選定
- 4.4.効果的な進め方のポイント
- 4.4.1.明確な目標を設定
- 4.4.2.積極的に参加できる環境作り
- 4.4.3.フィードバックを行う
- 5.OJT研修のメリットとデメリット
- 5.1.メリット
- 5.1.1.実務に直結した教育ができる
- 5.1.2.スピード感早く改善できる
- 5.1.3.一体感が深まる
- 5.2.デメリット
- 5.2.1.指導者により研修の質にばらつきが生じる
- 5.2.2.OJT研修のみでは得られないこともある
- 6.OJT研修を成功させるためのポイント
- 6.1.ポイント①目標設定の重要性
- 6.2.ポイント②指導者育成の方法
- 6.3.ポイント③コミュニケーションを円滑にする
- 6.4.ポイント④OJT制度運用の見直しと改善
- 7.OJT研修と他の手法の組み合わせ
- 7.1.OFF-JTとの効果的な連携
- 7.2.オンラインやリモート環境での実施
- 7.3.eラーニングの活用
- 8.OJT研修の実施事例と成功例
- 8.1.成功事例の特徴
- 8.1.1.明確な目標設定ができている
- 8.1.2.進捗管理がしっかりしている
- 8.1.3.具体的なフィードバックが行われている
- 8.2.失敗例から学ぶ注意点
- 8.3.事例に基づく実践アイデア
- 9.効果的・効率的にOJT研修を行いたい担当者様は「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
OJT研修とはなにか

OJT研修は「On the Job Training」の略称で、職場での実務を通じて職務に必要なスキルや知識を習得するための育成手法です。新入社員や若手社員が全体の業務を理解し、実践的な能力を高めるために、経験豊富な先輩社員が指導者となります。実際の業務に即した教育が行われるので、効果的に経験を積むことができます。
また、OJT研修は座学だけではカバーできない実務経験を提供するため、特に新入社員の早期戦力化といった目的において非常に有用です。教育を受ける側は、即座にフィードバックを受けながら作業を進めるため、理解度も高まりやすくなります。実践に基づいた学びを通じて、業務の効率向上を目指すことが、OJT研修の大きな特徴と言えるでしょう。
OJTとOFF-JTの違いとは?
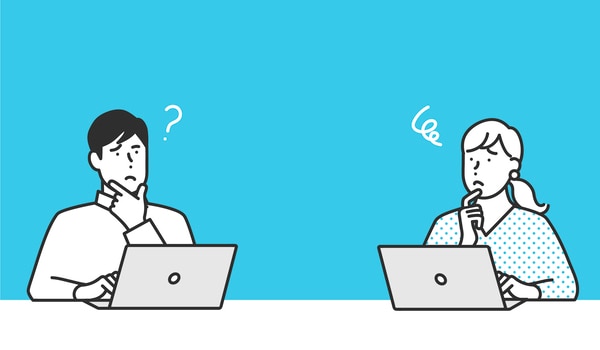
OJTとOFF-JTは、効果的な人材育成のために用いられる異なる研修手法です。この2つの手法を適切に使い分けることによって、より効果的な人材育成が実現できるでしょう。
OJT
OJTは「On the Job Training」の略称で、職場での実務を通じて学ぶ形式です。この研修は、実際の業務を行う中で、先輩社員や指導者による指導を受けながらスキルを身につけることができます。
OJTの利点としては、実践的なスキルを直接学べるため、新入社員や若手社員が即戦力として業務に貢献することが期待されます。また、現場のフィードバックを通じて、自らの成長を実感できる機会が多い点が魅力です。
OFF-JT
対照的に、OFF-JTは「Off the Job Training」と呼ばれ、職場外で行われる研修を指します。一般的には教室形式やオンライン形式のセミナー、講義など、理論的な知識や専門的なスキルを学ぶことに重点を置いています。教材やカリキュラムが整備されているため、幅広い層の新入社員や若手社員に対して一律の内容を提供できる特色があります。
OFF-JTは理論をしっかりと学ぶため、知識の基盤を構築するのに適しています。しかし、実務には必ずしも直結しないため、実践を伴うOJTと組み合わせて活用することが望まれます。
OJTとOFF-JTについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
↓
OJTとOFF-JTの違いは?それぞれのメリットやポイントを解説
OJTの目的と特徴

OJTの目的と特徴についてみていきましょう。
OJTの目的
OJTの主な目的は、職場での実務を通じて新入社員や若手社員が必要なスキルや知識を迅速に習得させることです。特に、実践的な業務に即した教育が行われるため、実際の業務を行いながら、現場で必要な能力を身につけることができます。これにより、勤務初期から即戦力として活躍できるようになることが期待されます。
OJTの特徴
OJTの特徴として、実践に基づいた学習が挙げられます。座学では得られないリアルな体験を通じて、新入社員や若手社員には高度な問題解決能力が求められます。トレーニングを実施する先輩社員や指導者が、業務の流れや重要なポイントを具体的に示すことで、学習効果が高まります。
また、新入社員や若手社員がその場で感じた疑問や課題に対して即座にフィードバックを受けることができるため、理解が深まりやすいです。
OJTはコミュニケーションを促進する場でもあります。指導者や他のメンバーと直接やり取りをすることで、チーム内の人間関係が構築されやすくなります。
OJT研修の具体的な実施方法

ここではOJT研修の具体的な実施方法について解説します。
OJTの4段階ステップ
OJT研修を成功させるための基本的な流れとして、4段階ステップが有効です。
ステップ①「見せる」
最初のステップは「見せる(Show)」ことで、指導者が実際の業務を行い、新入社員や若手社員にその手順を示します。この段階で、業務の全体像を把握できます。
ステップ②「説明する」
次に「説明する(Tell)」フェーズでは、指導者が業務の背景や注意点について詳細に説明します。このプロセスを通じて、新入社員や若手社員はなぜその方法が重要であるかを理解することができます。
ステップ③「やってもらう」
その後の「やってもらう(Do)」では、新入社員や若手社員が実際に業務を行い、指導者からの指導を受けます。
ステップ③「評価する」
最後に「評価する(Check)」段階で、新入社員や若手社員の成果を確認し、必要に応じてフィードバックを行います。
この4つのステップを繰り返すことで、理解が深まり、スキルの定着が図れるでしょう。
OJTの計画とスケジュール作成
OJT研修を計画する際は、具体的なスケジュールが不可欠です。まず、研修の目的や目標を設定し、それに基づいて研修内容を具体化します。進め方を明確にするためには、各セッションの時間配分や使用する教材も決定しておく必要があります。
スケジュールが明確だと、新入社員や若手社員の進捗確認や問題点の把握が容易になります。定期的に進捗を評価し、必要があれば研修内容を調整することで、新入社員や若手社員がより効果的に学習できる環境を提供できます。特に、実施中に得たフィードバックは次回の計画に活かす重要なアドバイスになります。
柔軟性をもたせることで、新入社員や若手社員が主体的に学ぶことができるようになるため、自発的な成長にも繋がります。この一連の流れにより、OJT研修全体の質を高めることができます。
指導者の選定
OJT研修の効果を左右する重要な要素として、指導者の選定が挙げられます。指導者には、豊富な業務経験や指導力が求められますが、それだけでなくコミュニケーション能力が高いことも不可欠です。指導者が新入社員や若手社員と信頼関係を築くことができれば、的確なフィードバックやサポートが行えるため、研修効果が最大化されます。
さらに、指導者は業務における実践的な知識をもち、新入社員や若手社員が理解しやすい形での説明ができることが望まれます。あらゆる指導方法を適切に使い分けることで、新入社員や若手社員がその場で直面する課題や疑問に対して、具体的な対策を提案する能力も求められます。指導者が職場の文化や要求に精通していることで、より適切な指導が可能になります。
これらの条件を踏まえ、指導者を選定することで、OJT研修の質が飛躍的に向上することが期待されます。
効果的な進め方のポイント
OJT研修を効果的に進めるためには、いくつかのポイントがあります。
明確な目標を設定
まず、明確な目標を設定し、その達成に向けて進行することが大切です。新入社員や若手社員の成長を実感しやすくするためには、具体的なステップを示し、進捗を確認する機会を設けることが効果的です。
積極的に参加できる環境作り
新入社員や若手社員が積極的に参加できる環境を整えることも重要です。質問しやすい雰囲気を作り、新入社員や若手社員が自身の意見を表明できる場をもつことで、研修への参加意欲が高まります。指導者が新入社員や若手社員の意見を尊重し、フィードバックを活用する姿勢を示せば、より良い学びの環境が整います。
フィードバックを行う
最後に、OJT研修の後には振り返りの時間を設け、自身の理解や成長を確認する機会をもつことが効果的です。この振り返りを通じて、次回の研修に向けた課題を抽出し、OJTの成果を最大限に引き出すことが可能になります。
OJT研修のメリットとデメリット

次にOJT研修のメリットとデメリットについてみていきましょう。
メリット
まずはメリットについて解説します。
実務に直結した教育ができる
OJT研修の最大のメリットは、実務に直結した教育が行える点です。新入社員や若手社員は現場で実際の業務を体験しながら、必要なスキルや知識を学ぶことができます。このため、座学では学ぶことのできない難しい状況に応じることのできる対応力や臨機応変な判断力を養うことが可能です。
スピード感早く改善できる
また、OJTを通じて新入社員や若手社員は指導者から直接フィードバックを受けることができるため、即座に改善点を把握することができます。これにより、誤った方法を長期間続けることを防ぎ、早期の成長がにつながります。
一体感が深まる
さらに、新入社員や若手社員は実務を行う中で職場の文化やルールを理解する機会も得るため、チームとの一体感が深まります。
デメリット
一方で、OJT研修にはいくつかのデメリットも存在します。
指導者により研修の質にばらつきが生じる
指導者のスキルや経験に依存する部分が大きいため、特に指導者の力量が不足している場合、研修の質が低下する可能性があります。指導者が適切な指導を行うためには自らの業務を見直す必要があるため、時間や労力がかかることもあります。
また、指導者としての役割を担う負担がかかることから、業務が過重になるリスクも考慮しなければなりません。
OJT研修のみでは得られないこともある
OJT研修だけでは新入社員や若手社員が専門的な知識を習得するためには不十分な場合があります。OJT研修は業務に特化した教育が行われるため、より広範な知識や汎用的なスキルを学ぶためには、OFF-JT等の別の研修手法との併用が必要です。
OJT研修を成功させるためのポイント
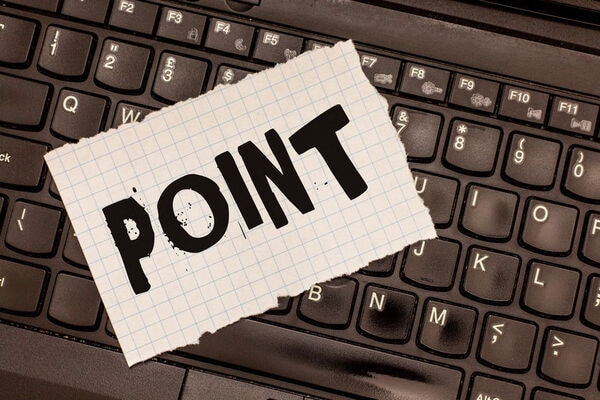
OJT研修を成功させるためには抑えておきたいポイントが4つあります。それぞれ詳しくみていきましょう。
ポイント①目標設定の重要性
OJT研修において目標設定は、新入社員や若手社員の成長を促進するために重要です。具体的な目標を設定することで、新入社員や若手社員は自分の進むべき道筋を明確に把握できます。例えば、「3ヶ月以内にこの業務を独り立ちできるようになる」といった具体的な期限を設けることで、新入社員や若手社員は自己の成長を自覚しやすくなります。
目標は、新入社員や若手社員がどのようなスキルを習得すべきかを示すものであり、指導者にとっても計画の指針となります。研修内容が目標に沿っていることで、指導者も進行を見直す際の参考になります。さらに、進捗評価の際に目標を基準とすることで、フィードバックがより具体的で意味のあるものになります。
ポイント②指導者育成の方法
効果的なOJT研修を実施するためには、指導者の育成が重要なポイントとなります。指導者は、実務におけるスキルや知識を新入社員や若手社員に伝える役割を担っていますが、指導力も求められます。そのため、指導者としての能力を高めるための研修やトレーニングが必要になります。
定期的な指導者向けの研修を開くことで、指導技術や教育メソッドを磨く機会を確保します。また、他の指導者と情報交換をすることにより、ベストプラクティスを共有し、自身の指導法を見直すことも有効です。新入社員や若手社員が効果的に学ぶためには、指導者自身も常に学び続ける姿勢が求められます。これにより、OJT研修がより質の高いものとなり、新入社員や若手社員の成長に貢献することができます。
ポイント③コミュニケーションを円滑にする
OJT研修において、コミュニケーションの質は非常に重要です。新入社員や若手社員が安心して質問や意見を述べることができる環境を整えることが、学びの効果を高めます。指導者がオープンな姿勢をもち、新入社員や若手社員との対話を積極的に促すことで、信頼関係が築かれます。
具体的には、定期的なフィードバックや1対1の面談を設けることで、新入社員や若手社員の考えや不安を受け止める姿勢が求められます。これにより、新入社員や若手社員が自信をもって学ぶことが可能になり、研修内容への理解が深まります。良好なコミュニケーションは、職場全体の雰囲気を良くする効果もあり、チーム全体のパフォーマンス向上にも繋がります。
一方的な指導ではなく、双方向のやり取りを重視することで、OJT研修の成功につながります。
ポイント④OJT制度運用の見直しと改善
OJT研修の制度運用を見直すことは、研修の質を向上させるために不可欠です。実施後には、その成績や新入社員や若手社員のフィードバックを基に、制度の評価と改善を行うことが重要です。定期的に運用の効果を測定し、どの部分が機能しているのか、改善が必要な点を把握します。
また、他部署や他社の成功事例を参考にすることで、新たな取り組みや手法の導入が可能になります。運用を柔軟に調整し、変化する業務環境に対応できる体制を整えることで、OJT研修の効果を最大化できます。
改善案を社員に説明し、新たな取り組みへの理解を深める努力も必要です。これにより、研修制度に対する信頼感が高まり、新入社員や若手社員が積極的に参加する意識が育まれます。OJT制度を継続的に見直すことで、変化に対応した研修を実施し続けることが可能となります。
OJT研修と他の手法の組み合わせ

OJT研修だけではなく、様々な手法を組み合わせると効果的です。
OFF-JTとの効果的な連携
OJTとOFF-JTの組み合わせは、新入社員や若手社員にとって非常に効果的です。OFF-JTでは、座学やセミナー形式で理論的な知識を学ぶことができ、これを基にOJTで実践的なスキルを身につけることが可能になります。例えば、業務の基本的な流れをOFF-JTで学んだ後、OJTでその内容を実際に取り入れることで、理解が一層深まります。
この連携により、新入社員や若手社員は知識を実践に活かすことで、より高いレベルのスキルを得ることができます。また、OFF-JTで培った理論背景が、OJTでの業務に対する正確な理解を助ける役割を果たします。全体として、両者が補完し合うことで、より効果的な教育プログラムを実現することが可能です。
オンラインやリモート環境での実施
最近では、オンラインやリモート環境におけるOJT研修が注目を集めています。特に、地理的な制約を超えて研修を実施できるため、様々な場所にいる新入社員や若手社員に対して同時に教育を行うことができます。リアルタイムのビデオ会議やオンライン協働ツールを活用することで、効率的な指導が可能となります。
リモート環境では、新入社員や若手社員が自分のペースで進められる柔軟性が提供されるため、働き方に合わせた学習が促進されます。
また、オンラインでは多様な教材やリソースを取り入れることができるため、視覚的な学びを強化することも可能です。これにより、失敗を恐れずに新入社員や若手社員が実践を重ねられるため、結果としてスキルの習得が促進されます。
eラーニングの活用
OJT研修を進化させる手段として、eラーニングの活用も重要です。eラーニングプログラムを用いることで、新入社員や若手社員は必要な知識をいつでも、どこでも学ぶことができます。特に、基礎知識や共通スキルをオンラインで習得することにより、OJT研修時の実務にシームレスに接続される環境が整います。
新入社員や若手社員がeラーニングを利用することで、学習内容を自分のペースで確認し、再学習が容易に行える点も大きな利点です。
さらには、新入社員や若手社員は動画などを通じて、視覚的な理解を深めることができるため、記憶に残りやすくなります。
弊社のeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」は、OJT研修にも活用することができます。
自社オリジナルの研修内容や問題を搭載し、受講者に応じてコンテンツの出し分けができるので、簡単に受講者のニーズにあった研修を実施することが可能です。
OJT研修の実施事例と成功例

ここではOJT研修の事例についてご紹介します。
成功事例の特徴
成功事例に見られる3つの特徴をみてみましょう。
明確な目標設定ができている
成功事例に見られる特徴の一つは、明確な目標設定です。具体的に何を達成すべきかが明示されている研修プログラムは、新入社員や若手社員にとって目指す方向性が明確になります。これにより、新入社員や若手社員は自発的に行動しやすくなり、研修そのものへの参加意欲も高まります。
進捗管理がしっかりしている
次に研修の進捗管理がしっかりと行われている点も挙げられます。定期的に進捗を評価し、達成度を確認することによって、新入社員や若手社員は自分の成長を実感できます。
具体的なフィードバックが行われている
フィードバックが具体的であり、改善点が明瞭に示されることで、次に向けた取り組みが促される環境が整います。
失敗例から学ぶ注意点
OJT研修の失敗例を振り返ることも非常に重要です。
多くのケースで見られる問題は、目標設定が不十分であったり、指導者の指導力が不足していることです。特に、研修の初期段階で明確な目標がなければ、新入社員や若手社員は何に重点を置いて学ぶべきか不明瞭になり、モチベーションが低下する可能性があります。
フィードバックが不足している場合、新入社員や若手社員は自分の進捗や課題に気づくことが難しくなります。特に悪い事例として多く見られるのは、評価が一方的なものであるため、新入社員や若手社員が自信を失ってしまう状況です。
こうした失敗から学ぶことは、指導方法の見直しや、コミュニケーションの重要性を再認識させるいい機会になります。
失敗事例を分析することで、改善に向けた具体的な施策を考えることができ、今後の研修に活かせる貴重な情報が得られます。
事例に基づく実践アイデア
OJT研修をより効果的に実施するためには、事例に基づいた実践アイデアを活用することが有効です。例えば、成功した企業の取り組みを参考にすることで、効果的な研修プログラムを導入できます。指導者が新入社員や若手社員それぞれの成長に気を配り、個別に対応する方法が成功の鍵となっているケースが多く見られます。
また、定期的な振り返りのセッションを組み込むことも重要です。新入社員や若手社員が自分の経験や学びを共有する機会を提供することで、相互の学びが深まります。その際に、参加者全員が意見を出しやすい雰囲気を作り、考え方を多様化させることがポイントです。
さらに、新入社員や若手社員に対して研修の重要性を再確認させるために、PBL(ProjectBasedLearning)などの手法を取り入れることも効果があります。実際のプロジェクトを通じて学べる経験が、業務に即したスキルを身につける手助けとなるでしょう。このような実践アイデアを導入することで、研修の効果を一層引き上げることが可能です。
効果的・効率的にOJT研修を行いたい担当者様は「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」は、OJT研修に活用することができます。
自社で作成した教材を簡単に搭載できるため、オリジナリティの高い研修動画の作成が可能です。
さらに、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただけば、さまざまな対象にあわせた社内教育がすぐに実施できます。
「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートすることができます。
コンテンツには、新入社員向けのものや内定者教育向け、管理職向けなどを含む、100本を超える動画と、理解度を測定することができるビジネス問題が3,000問以上揃っております。
ぜひ「サクテス学びホーダイ」をご活用ください。
SAKU-SAKU Testingは、教育担当者様の声を反映したUIデザインで、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を主催する側・新入社員側、いずれも効率的に利用できます。
ご興味がおありの場合は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。