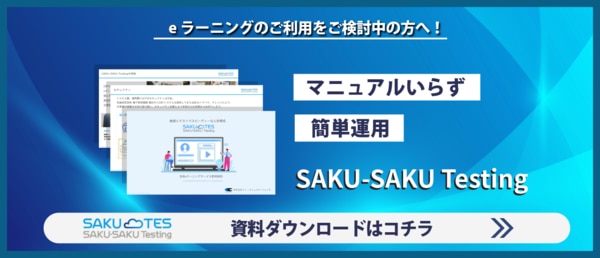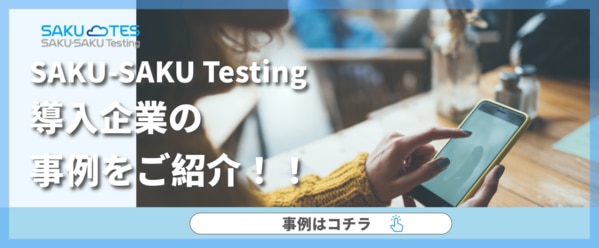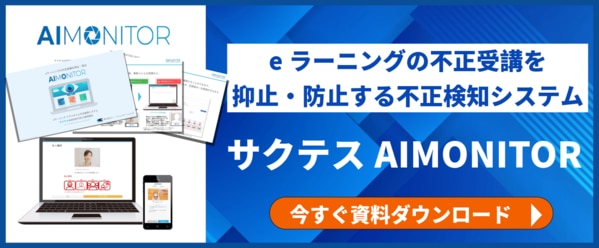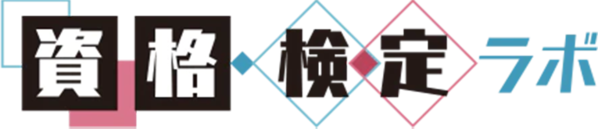ロジカルライティングで業務がスムーズに!中小企業に必要な文章力の底上げ法
「この文章、何が言いたいのかわからない…」
そんな声が社内で増えていませんか?
メールや報告書、チャットでのやりとりなど「文章を書く機会」は多くありますが、伝える力には個人差があり、ミスや認識のズレが起きることも少なくありません。
そんな悩みを解決するのが、ロジカルライティングです。
本記事では、ロジカルライティングの基本から、取り入れるメリット、すぐに使える書き方のポイントまでをわかりやすくご紹介します。
目次[非表示]
ロジカルライティングとは?

ロジカルライティングとは、伝えたいことをわかりやすく、筋道立てて書くためのスキルです。結論があって、それを支える理由や根拠がしっかりある文章は、読む人にもすっと伝わります。特にビジネスシーンでは、ちょっとした言い回しの違いで誤解が生まれたり、確認の手間が増えたりすることもあります。ロジカルライティングを身につけることで、社内外のやりとりがスムーズになり、文章が「伝わる」ものに変わっていきます。
ロジカルライティング導入のメリット

ロジカルライティングを社内に取り入れることで、文章の質が上がるだけでなく、日々の業務全体がスムーズに回りやすくなります。
ここでは、3つの大きなメリットをご紹介します。
①情報を正確に伝達できる
伝えたいことを筋道立てて整理することで、読み手に「正しく伝わる文章」になります。「つまり何が言いたいの?」と聞かれることが減り、認識のズレや確認の手間も少なくなります。報告や連絡、相談といったビジネス上のやりとりがスムーズに進むのが、ロジカルライティングの大きな強みです。
②情報をわかりやすく伝達できる
ロジカルライティングを活用すると、伝えたい情報を整理し、順序立ててわかりやすく伝える力が育ちます。この考え方は、文章だけでなく、会議での発言やメモの取り方にも活かせます。物事を筋道立てて捉えられるようになることで、相手にも自分にも「伝わる」工夫が自然とできるようになります。
③提案力を高められる
相手に「伝わる」文章が書けるようになると、提案の場でも役立ちます。ロジカルライティングは、相手が求めるポイントを整理し、要点を簡潔に伝える力を育てます。結果として、取引先や顧客に対して納得感のある提案ができるようになり、信頼関係の構築にもつながっていくはずです。
ロジカルライティングの書き方

ロジカルライティングは、特別な才能ではなく「コツ」で身につけられるスキルです。ここでは誰でも実践できる「書き方の基本」を3つに分けてご紹介します。
①誰に何を伝えたいのか?明確に
まず大切なのは、「誰に」「何を」伝えたいのかをはっきりさせることです。相手が上司なのか、取引先なのかによって、伝える内容や言葉選びは自然と変わります。たとえば、新しい企画について上司に伝える場合でも、「承認してほしい」のか「意見をもらいたい」のかで、書き方は異なります。目的が明確になると、読み手の関心に沿った構成や表現を選べるようになり、伝わる力がぐっと高まります。
②結論ファーストで書く
ロジカルライティングの基本は「結論ファースト」です。つまり、伝えたいことの要点を最初に書きます。たとえば、上司への報告メールなら「◯◯の件は、無事に対応済みです」と最初に結論を書くと、読む側が状況をすぐに把握できます。結論を後回しにすると、最後まで読まないと要点がわからず、誤解や確認の手間が生まれます。ビジネスでは、最初に答えを示すことが信頼にもつながります。
③簡潔に書く
伝えたいことをしっかり届けるには、できるだけ簡潔に書くことが大切です。長い文章や遠回しな言い回しは、読む側にストレスを与えています。一文の長さは60文字前後を目安に、「一文一義(ひとつの文にひとつの内容)」を意識しましょう。また、主語と述語を正しく対応させる、曖昧な表現を避けるといった工夫も、読み手の理解を助けます。無駄をそぎ落とした文章は、伝えたいことがすっきりと伝わります。
ロジカルライティングを活用した「メール」の事例

まずは以下の例文を見てみましょう。
とある営業マンがトラブルを起こし、上司に報告メールを送っています。
「お疲れさまです。○○プロジェクトの件でご報告があります。今朝、A社との打ち合わせ中に、先方の要望と当社の提案内容に食い違いがありました。その場では説明がうまくできず、少し混乱が生じてしまいました。結果として、次回の提案内容を再検討することになりました。」
▼NGポイント
・要点(何が起きたか)が最後まで読まないとわからない
・読み手にとって「どうすればいいのか」の判断がしづらい
上記の文章を、ロジカルライティングを活用したメールに書き換えてみましょう。
「お疲れさまです。○○プロジェクトに関して、A社との打ち合わせ中に提案内容の齟齬があり、再調整が必要となりました。具体的には、先方の要望とこちらの提案に食い違いがあり、その場では意図が十分に伝わりませんでした。次回までに内容を再確認し、再提案いたします。」
▼改善ポイント
・最初に「結論(齟齬があり、再調整が必要)」を提示
・背景→対応策の流れがわかりやすく、読む側が理解しやすい
このように文章の順序を「結論→理由→詳細説明」に変えるだけで、読み手の理解度や判断スピードは格段にアップします。
ロジカルライティングに最適な3つの文章の型

ロジカルライティングには異なる文章の「型」があります。使い分けることで、誰でも伝わりやすい構成を作ることができます。
ここでは、ビジネスシーンで特に使いやすい3つの型をご紹介します。目的に応じて、使い分けてみましょう。
①逆三角形型
逆三角形型は、「要点→詳細→補足」の順で構成する文章の型です。最初に伝えたい結論を示すことで、読み手は冒頭だけで全体像をつかむことができます。その後に詳しい情報や背景を加えていくため、時間のない相手にも要点が伝わりやすく、ニュース記事や報告文などに適しています。
②情報列挙型
情報列挙型は、主題に対して複数のポイントを順に並べて説明する文章構成です。「3つのコツ」「5つのポイント」など、体系的に整理された内容を伝える際に効果的です。冒頭でテーマを明示し、その後に具体的な要素を列挙していくため、読み手にとって理解しやすく、ブログ記事などでよく使われます。
③PREP法
PREP法は、相手に納得してもらいたいときに効果的な文章構成です。「結論→理由→具体例→結論」の順で伝えることで、説得力のある文章になります。冒頭で主張を明確にし、根拠や実例で補強したうえで、再度結論で締めくくるため、話の流れがスムーズで印象にも残りやすく、プレゼン資料や提案書などに適しています。
まとめ

ロジカルライティングは、誰でも身につけられるビジネススキルです。
伝えたいことをわかりやすく書けるようになると、業務のムダやミスが減り、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。
まずは基本の型を意識し、日々の文章に少しずつ取り入れていきましょう。
社員のスキルアップにeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください
本記事では、ロジカルライティングを向上させるための方法やポイントについてご紹介しました。
eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」では、自社に必要なスキルにあわせたオリジナルコンテンツを搭載することができます。取り組みの進捗など、管理画面から簡単に確認することができます。
SAKU-SAKU Testingは、教育担当者様の声を反映したUIデザインで、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を主催する側・受講者側、いずれも効率的に利用できます。
ぜひ、社員のスキルアップに「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください。
また、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただけば、さまざまな対象にあわせた社内教育がすぐに実施できます。
「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートすることができます。
コンテンツには、新人社員向けのものや内定者教育向け、管理職向けなどを含む、100本を超える動画と、理解度を測定することができるビジネス問題が3,000問以上揃っております。
ご興味がおありの場合は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。